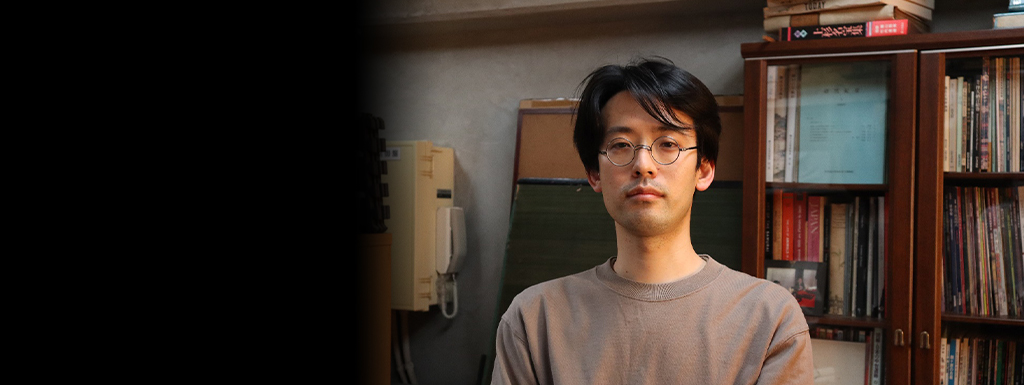- 小
- 中
- 大
神奈川県横浜市で日本甲冑を制作修理する「西岡甲房」で、甲冑師の「西岡文夫」(にしおかふみお)氏のもとで日本甲冑を日々修理し、甲冑への理解を深めるために心を砕く「大野思惟人」(おおのしいと)さん。
今回、大野思惟人さんにインタビューを行い、甲冑師を志した理由、仕事の難しさと楽しさ、大事にしていることや将来の目標を伺いました。
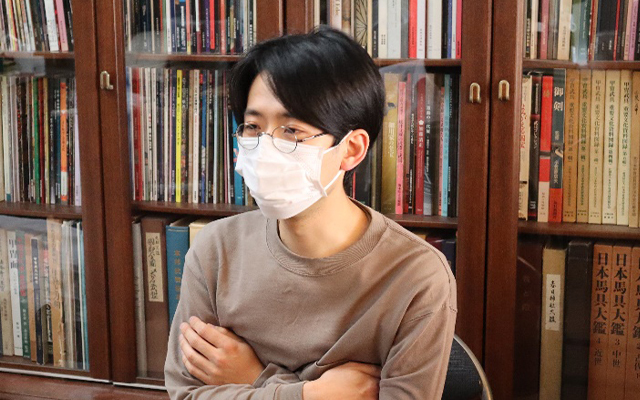
-
大野思惟人(おおのしいと)さん
- 1988年生まれ。東京都出身
- 多摩美術大学にて鍛金を、東京芸術大学大学院では文化財保存学を専攻する
- 大学院在学時より甲冑師の西岡文夫氏に本格的に入門し、2022年現在は西岡甲房で、各所からの依頼を受けて古甲冑の修理や甲冑新作にかかわる
1甲冑師を志すまで
「甲冑師」という仕事をされているからには、大野さんは甲冑がとても好きなのだと思います。甲冑に興味を持ち始めたきっかけはありますか。
大野思惟人さんもともと子供のころからモノづくりが好きでした、小学生の頃から歴史も好きになり、その2つの「好きなもの」が結びついて甲冑への興味が強まりました。
特に、2000年(平成12年)放送のNHK大河ドラマ「葵 徳川三代」から影響されて「甲冑を作りたい」という思いが芽生えました。劇中の関ヶ原合戦のシーンなどには「変わり兜」(かわりかぶと)がたくさん出てきたこともあって、最初は変わり兜に魅せられていました。
「甲冑が好き」という気持ちはあっても、実際に甲冑師になるのは大変なことでしょう。師匠の西岡文夫(にしおかふみお)先生とはどのように出会いましたか?
大野思惟人さん「笹間良彦」(ささまよしひこ)さんという日本甲冑の研究家がいましたが、笹間良彦さんの本を発行していた出版社に、甲冑を作っている方を教えていただきたいと手紙を書いて問合せをしたら、西岡文夫先生に連絡をつないでいただいたのが最初です。
実際に初めてお会いしたのは、私が高校2年生だった2005年。西岡文夫先生は、山梨県立博物館(山梨県笛吹市)からの依頼で国宝「小桜韋威鎧」(山梨県・菅田天神社所蔵)の復元模造を制作していた最中で、多忙にもかかわらず、制作作業を見せて下さいました。また、平成のはじめに赤糸威鎧(東京都・武蔵御嶽神社所蔵)の兜を模造したとき、1回仕上げたあとに寸法(すんぽう)が原資料と数ミリ合わないのをどうしても納得できずにやり直したという話をお聞きし、仕事に対する熱意や厳しさも感じました。

甲冑師になるには相当な覚悟が要ったことと思います。そのとき周囲の反応はいかがでしたか?
大野思惟人さん西岡文夫先生は「甲冑師になりたい」と願っていた私に対して、「[甲冑師には]なれないからやめておきなさい」や「[甲冑師では]食べていけない」とおっしゃいましたが、「好きなことをやれたら面白いだろう」としか思っていなかった当時の私は、その意味を理解できていませんでした。
家系に建築や絵画を教えていた人がいることもあったのか、両親は反対しませんでした。私がモノ作りに携わることに抵抗はなかったようです。弟がいて、水産関係の仕事に就きましたが、今は組紐(くみひも)など私の作業を手伝ってくれています。
医者志望の友人からは「そんな仕事に就くな、ちゃんとしろ」と言われましたが、「甲冑師をどうしてもやりたいんだ」と説明していました。
高校卒業後に多摩美術大学、さらに東京芸術大学大学院へ進学されますが、現在の日本の美術大学には甲冑を直接勉強できる環境がない中、どのようなことを学んだのでしょうか。
大野思惟人さん多摩美術大学に進学したのは、西岡文夫先生からも「[甲冑師になるには]まず美大を出てから」と言われたことが理由のひとつかもしれません。それは「進学して[本当に甲冑師になりたいかどうか]考え直したら?」という文脈でのことだったと思います。
最初は鍛金(たんきん:金属をたたきのばして器物を形作る工芸)をやりたかったので、学部のときはそちらを学びました。その後、文化財にかかわることも勉強したいと思い、学部卒業後は東京芸術大学大学院に入学し、文化財保存学を専攻しました。同時に西岡甲房(にしおかこうぼう)へも通うようになり、本格的に甲冑師修行が始まったわけです。大学院では主に漆を勉強し、大学の附属美術館が所蔵する甲冑で傷んでいた物を修理する経験もさせていただきました、特に甲冑関連の事柄は西岡甲房や日本甲冑武具研究保存会での先生方、先輩方のお話や貴重な実物の観察を通して勉強させていただきました。

甲冑師になろうと決心した出来事はありますか?
大野思惟人さん大学時代に旅行で青森県八戸の櫛引八幡宮(くしひきはちまんぐう)を訪れ、国宝の大鎧を鑑賞したことが甲冑師を目指す上での決定的な経験でした。多種多様の豊富な材料を自分の中に落とし込み、1領の甲冑に仕上げていくことが魅力的に感じられ、以前からの甲冑師になりたいという思いがいっそう強まりました。そのときは赤糸威鎧を観るのが目的だったのに、むしろ隣に飾られていた白糸褄取威鎧に惹かれてしまいました(笑)。
在学中の経験は、現在の仕事や価値観にどうつながっているかを教えていただけますか?
大野思惟人さん大学での授業や活動を通して、文化財関係の様々な技法を試すところや、成功例や失敗例を多く見ることができ、美術工芸の技能や考え方を自分の中だけで完結させず、広い視野でとらえることの大切さを実感しました。また、現在でも交流している人がいることはとてもありがたいことです。鍛金をやった学部では作家や教員になった人が多く、大学院での知人には彫刻や絵画の修復に携わる人がおり、時々質問や話が伺えることが勉強になります。
2甲冑師修行について
甲冑師として、最初の見習い段階ではできることが限られていたと思いますが、どのような作業を中心にやりましたか?
大野思惟人さん西岡甲房の仕事は甲冑の修理が多いです。最初は錆やほころびなどの破損した部分を解体する作業を任していただきました。例えば鉄の部品に赤錆が生じたら、そこから朽ち込むので落とさなければいけませんが、漆が塗られた内部で錆が進行している場合は、漆を剥がすことがあります。胴(どう)や袖(そで)の縅毛(おどしげ)が劣化していれば交換が必要な場合があります。状態次第では甲冑を「札板」(さねいた)まで交換することになります。修復過程は、破損した部分を詳しく観察することができ、外見からは分かりにくい甲冑の構造や部品の組み立て方のほか、時代による形の移り変わりや部品の取り付け方の違い、オリジナルの部分と後世の修理改造の区別などを学べます。
特に、「覆輪」(ふくりん:縁を金・銀で飾ること)がすべて外れた「阿古陀形筋兜」(あこだなりすじかぶと)の修復にかかわらせていただいたことは勉強になりました。実際に組み上げようとすると、一定の手順を踏まないと各部品がきれいにまとまらないことが分かり、はじめは「どうしたものか」と悩みました。現代の自動車製造工程にも、車種やブランドごとに組み立て方の順番があるのと同様に、当時の甲冑にも組み立て手順が存在していたのですが、それを追体験できたのが大きな収穫でした。

大野思惟人さんが西岡文夫先生に入門してから約10年が経ち、今は様々な仕事を任されていると思われますが、その中で特に難しいと感じる作業は?
大野思惟人さん10年程度で分かることは限られていると思いますが、甲冑を修理する上では、壊れたり失われたりした部品を直すとき、他から補ったり新たに作ったりするのですが、どちらにしてもその甲冑の「時代観に合わさった、雰囲気を損ねない」ものを用意することが一番難しいと思います。
例えば胴の「胸板」(むないた)や「脇板」(わきいた)といった、「金具廻」(かなぐまわり)が欠けているのを補おうとしても、甲冑の作られた時代には存在しない形やデザインの物を合わせると、違和感が強まり破綻してしまいます。よく車で例えるのですが、スポーツカーに軽トラックの部品が付いていたり、異なるブランドの部品が付いていた場合、車に詳しい人が見ると、不自然さを覚えるのではないでしょうか。

甲冑を実用していた時代なら、制作時期が異なる部品で欠損を補うこともあったでしょうし、現にそうと見られる遺品が残っていますが、甲冑を文化財として保存することが重視される現代では、時代観のすり合わせが重要になりますね。
大野思惟人さん時代ごとに流行した形状や装飾技法の傾向を把握することが、非常に重要ではないかと思います。もちろん、時代の定型からずれた例外的な作品もありますので、様々なパターンを吸収していきたいと強く考えています。模造甲冑を新作する際も、見かけだけをまねるのではなく、当時の人が実際に甲冑を着て戦う際に重視していただろう、着心地とか歩きやすさ、防御力などの使い勝手や機能性を意識して、部品ひとつひとつの材質や形に着目し、細かい配慮に気付ける感覚をつかんでみたいです。
漆の色味を調整する苦労話を度々耳にしますが、それもやはり苦心される分野ですか?
大野思惟人さん確かに、漆の色味が合っていないのも嫌な気分になります。とりわけ、朱漆の明暗や古びた感じを計算して調合するのが難しいです。漆の修理は剥がれた部分を新しく塗ることが多いですが、修理した部分の漆の色彩が周囲から浮いてしまうと、甲冑を鑑賞してもそこだけが強調されてしまい、甲冑全体の姿や雰囲気が頭の中に入らないことがよくあるのです。ただし、修理箇所が明らかに分かる方が良いという意見もあり、依頼者の考えを尊重し、それに合わせて幅広く対応できるようにしたいです。
西岡甲房では新作も手掛けることがありますね。仕事として修理と新作の割合はいかがですか?
大野思惟人さん数で言うと修復の方が多いです。甲冑の新作依頼は、制作期間が長いこともあり多くないですが、いつでも新作に挑戦したい気持ちはあります。
ライフワークとして挑戦したい甲冑があれば教えていただけませんか?
大野思惟人さん南北朝時代の「四方白総覆輪星兜」(しほうじろそうふくりんほしかぶと)は仕事でなくとも作ってみたいです。私は分からないことをそのままにできず、全部理解してからでないと行動に移せない性格で、夢は膨らみますが、やり方が分からない制作技法や構造があると先に進めません。覆輪の色味の出し方がまだ分からないです。
昨年、島根県の甘南備寺(かんなみじ)が所蔵する重要文化財の「櫨匂威鎧」(はじにおいおどしのよろい)を観ましたが、大変興味深いです。現状は小札板(こざねいた)がバラバラですが、本来の姿を想像復元できるのではという気がします。兜鉢(かぶとばち)や金物(かなもの)など、残っていない部分は可能性の高いものから想像するしかないのですが(笑)。
ただ、復元品を作るならば、後世の人がそれを観て「当時の甲冑の研究水準からして、この時代の甲冑師が採り得た最適な選択肢だ」と納得できる物を作りたいです。「この程度か」と言われる物にはしたくありません。

古い甲冑の修理ですと、過去にどのような修理を受けてきたのかというのも気になりませんか?なかには適切と言えない手法で直されてしまった物もあるかと存じますが、そのような場合はどう対応されますか?
大野思惟人さん部品の位置を間違えて取り付けたなど、現在の甲冑研究の知見からは不適切な修理を施された甲冑がやってくる場合もあります。しかし、長い間その状態で伝わってきたために、甲冑を所蔵する方や、地域の方には「誤った姿」の方がなじみ深いこともあるようです。
甲冑修理では「どのように修理するべきか」ということだけでなく、「この部分は直すべきか、そのままにしておくのが良いか」ということもよく考えます。とは言え、甲冑を修理するとき「誤った状態」を維持することにして、それを現在の関係者は理解していても、年月が経ち世代が代わる中で情報が伝聞になり、未来にはそのことが分からなくなってしまうおそれもあるのではないでしょうか。
甲冑師の仕事を通じて、「伝えること」の大切さを痛感します。修理の前後を比較でき、どんな方法で修理したかも分かるように、調査記録や修理報告書を作成すべきと考え、実際そのようにしています。最近は、博物館や寺社などから所蔵品の甲冑修理依頼が増えてきていますが、そうした甲冑を目の前にすると、長い間伝えてきた方々の思いを感じ、仕事に対する責任を意識します。
「名古屋刀剣ワールド」は、日本刀や甲冑、浮世絵をメインにする博物館として、展示や活動を通じて甲冑の魅力や楽しさをより身近な方法で伝えていきたいと考えますが、甲冑師として博物館に求めることはありますか?
大野思惟人さん現在の家庭には甲冑がある家は少ないので、まずは甲冑を身近に観て貰いたいと思います。博物館では色や形といった見た印象のインパクトだけでなく、重さや素材など触れなければ分かりにくい感覚的な部分も伝わるような展示をしていただきたいと思います。色んな意味で甲冑に触れられる機会が必要です。
友人達とどのようにすれば伝わるのか、どう言うことを知りたいのかというのはよく話しているのですが。見せるだけの展示では難しいですが、キャプションに重量の数値があると、観る人は具体的に想像しやすくなるのではないでしょうか。「胴は重いけど、草摺は意外と軽いのね」、「バランス悪く見えるけど、軽いのならなんとかなるのかな」、「これを着て馬に乗るのは大変そう」というふうに感じてもらえると印象が変わってきます。さらに、一口に「籠手」(こて)と言っても色んなタイプがあり、装着の仕方の違いとか、腕の動きを考えて部品が付いているなどを他と比較できると現在では思いつかないような発想のものもかなりあり、圧倒されてかなり興味深いと思います。外観から推測したり判断したりするのが難しい点が伝わると嬉しいです。材質による硬度の違い、高級な裂を使っているなど、作業する際に細かく観察できる自分達だからこそ、気付ける点はありますが、それを見るだけでなく短い時間で伝えるのは難しいと思います。

昨今はコロナ禍で難しくなりましたが、近年の博物館ではワークショップやレプリカを用いた触(さわ)れる展示も増えてきています。ただ置いて観てもらうだけではない、理解しやすい展示を充実させるためには、モノを作る側と展示研究する側とがもっと協力していく必要があると考えますが、最近そのような活動をされたことはありますか?
大野思惟人さん博物館からの相談で多いのは、小札の種類の模型や、組み立て工程の動画作成です。高校生の頃、テレビ番組で「蒔絵[まきえ]手箱の作り方」を見たことがありますが、手箱を作る全工程のほんの一部しか放送されなかったとしても、私にとっては大いに勉強になった経験があります。博物館の甲冑展示では、縅毛の色目や兜の種類を紹介することが多いですが、そればかりではさびしい、もったいないと思います。

3「感覚」を求めて
大野思惟人さんのお話を伺っていますと、「感覚」が仕事の軸になっているように感じられます。
大野思惟人さん仕事をしているとき、自分には感覚的な部分が足りないと、常に飢えた気分や不安を覚えています。私の友人に「百姓になりたい」と言う人間がいて、その友人いわく「種まきの時期や縄の組み方など、ひとつひとつ百の仕事のできる百姓としての感覚を知りたい」とのこと。それと似た気持ちでしょうか。高校時代に彼らと過ごしたことが、私の感覚に対する関心のもとになっているように思います。
加えて西岡文夫先生や故「上野修路」(うえのしゅうじ:金工を主として、中世日本の美術工芸の復元に力を注いだ工芸家)さんに、制作時に気が付いたこと、現物と比較しての違いや、当時の職人がどのような考えをもっていたのではないかなどのお話を伺って、さらに感覚を求める気持ちが強まりました。
他にも普段甲冑を観ない人が鑑賞したときに抱く印象や、甲冑を研究する方の様々なお話をお聞きしたいです。常に甲冑を身近に見すぎているために、大切なことをかえって見落としているのではという警戒心があります。
今後の目標について教えていただけますか?
大野思惟人さん今は目の前の仕事で精いっぱいですが、余裕があれば修理などでかかわった甲冑の情報をまとめていきたいです。あとは「新甲冑師銘鑑」の内容も更新したいし、昔の売立目録に掲載された甲冑の情報も整理したい。やりたいことがたくさんあります。一番はもっと感覚的な部分をつかめるようになりたいとおもいます。昔の人と同じような目線で甲冑を作れるようになることが重要な目標で、そのためには当時の人が感じ取っていた時代観を的確につかみ、現時点でやり方の分からない技法の解明につながる感覚を鍛えていくことが不可欠と考えます。
甲冑を通して現代人としての自分を表現するのではなく、今まで伝わってきた甲冑を守るということに主眼を置いて活動していきたいです。
この仕事をしていて良かったと思うときは?
大野思惟人さんちょっとしたことでも疑問が解決した(かもしれない)と思える瞬間と、また新たな疑問にぶつかる瞬間を日々繰り返して刺激を得られることかもしれません。モノを作っていけること、でき上がっていく過程に立ち会えることはずっと好きですね。やはり一番嬉しいのは、かかわった修理を喜んでいただくことです。
*インタビュー:2022年4月