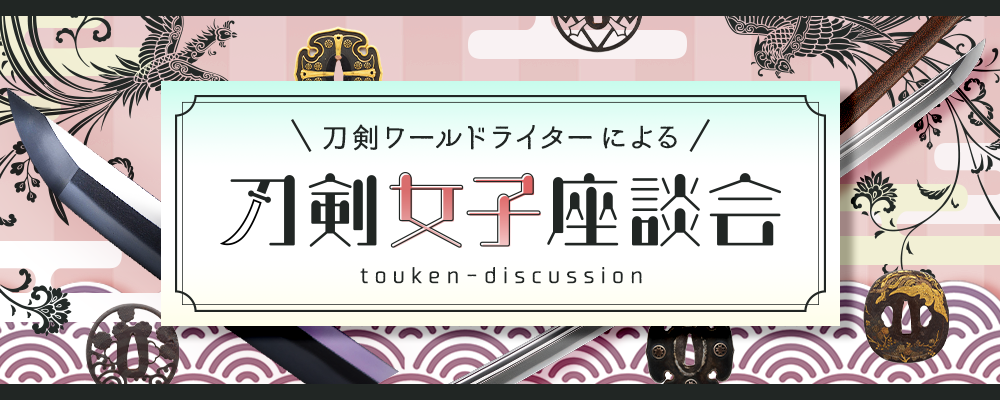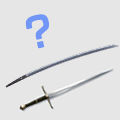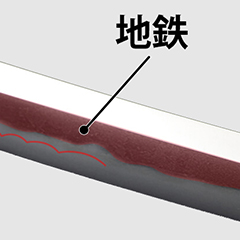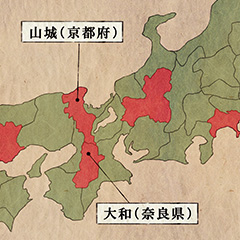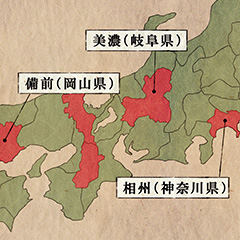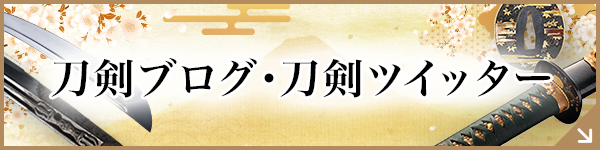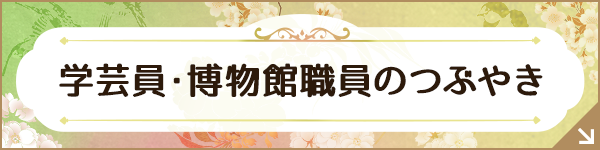第1回
好きな日本刀(前編)
刀剣女子のライター達による座談会。記念すべき1回目となる今回のテーマは「好きな日本刀」について!普段から様々な日本刀に触れているライター達が、実在する名刀や「隕石」で作られた刀剣など、それぞれが「推し」の刀について語ります!

今回の参加者
-
 つばめ
つばめ
-
 みそ
みそ
-
 青虫
青虫