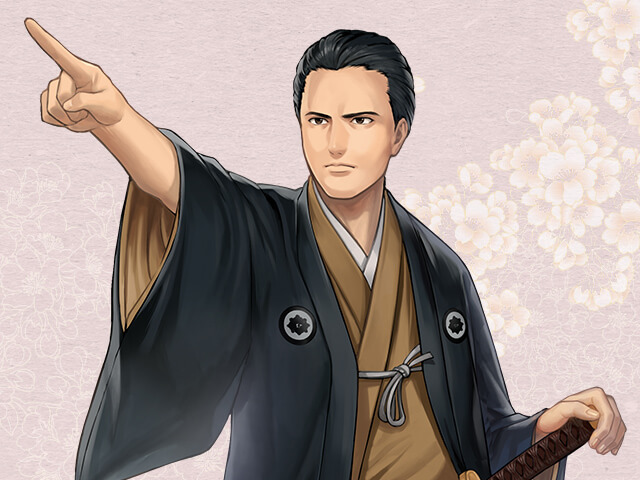大河ドラマに見る武士道 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
新しいコンテンツが台頭してはいますが、我々にとって一際馴染み深いのはやはりNHKの大河ドラマではないでしょうか。1963年(昭和38年)に放送が開始された歴史ドラマシリーズの総称で、日本の歴史上のできごとや偉人に焦点を当てた内容になっています。史実・定説をベースにしながらも、ときには架空の人物を登場させたり、斬新な演出を用いたりといった展開もあり、老若男女を問わず支持されてきたコンテンツと言えます。
近年では様々な方法で海外でも視聴が可能となっており、「大河ドラマがきっかけで日本の歴史に興味を持った」という外国人の声を聞くことも増えました。そんな大河ドラマのなかでも特に武士道精神が見て取れる作品、主人公に据えられた人物達の逸話などをご紹介します。
真田丸(さなだまる)
三谷幸喜氏、大河2回目の脚本は武士の生き方や家族愛を盛り込んだ名作
「真田丸」(さなだまる)は2016年(平成28年)1月から1年間に亘って放送された、55作の大河ドラマです。本作では大坂冬の陣・夏の陣での奮戦ぶりが有名で、「真田幸村」(さなだゆきむら)の別名でも広く知られる武将「真田信繫」(さなだのぶしげ)が主人公に据えられました。
真田信繫役を演じたのは、俳優の「堺雅人」(さかいまさと)さん。脚本は「三谷幸喜」(みたにこうき)さんが手がけました。
放送が開始されると、ときに苛烈に、ときにユーモアたっぷりに描かれる真田信繫やその家族の人生に魅了される視聴者が続出。視聴率は過去5年の大河ドラマのなかで最高を記録し、真田ゆかりの地やドラマ撮影地への観光客の増加、ドラマのロゴや登場人物がラッピングされた列車が運行されるなど、様々な社会現象も巻き起こしました。
真田信繫と武士道
真田信繫の武士道、そのルーツは上杉家にあった?
真田家はもともと武田家の家臣として信濃国(現在の長野県)の一部を治めていました。しかし君主である「武田勝頼」(たけだかつより)が「織田信長」に敗れ、武田家は滅亡してしまいます。
真田信繫の父で真田家当主の「真田昌幸」(さなだまさゆき)は、この戦乱の世を、ときに有力武将の家臣となったり、ときに小国をまとめあげて自立をしたりと、様々な策を講じて渡り歩いていきます。
その過程で上杉家に属することになった際、真田信繫は「上杉景勝」(うえすぎかげかつ)のもとへ人質という名目で送られますが、実際は家臣として厚遇され、「直江兼続」(なおえかねつぐ)をはじめとした上杉家家臣から、「義」の考え方を学んだとされています。のちに「日本一の兵」(ひのもといちのつわもの)と呼ばれる武士になったルーツのひとつはここにあったと言っても過言ではありません。
忠義を尽くし家も守る!兄・真田信幸の妙案で生き残る真田家
「豊臣秀吉」が台頭すると、真田家は豊臣氏に従属。この際、真田信繫は人質として大坂に移されます。真田家は豊臣秀吉のもとで北条氏討伐に参加するなどして、天下統一に貢献。真田信繫は豊臣の姓を下賜されたうえ屋敷を与えられるなど、一大名として扱われていました。
豊臣秀吉の没後は「徳川家康」が天下取りに動き、反発した豊臣方との間で、いわゆる「関ヶ原の戦い」がはじまり、全国の諸大名は徳川家康と豊臣秀吉、どちらに味方するかを決断することになります。
このとき真田家は、真田信繫が豊臣方の武将、「大谷吉継」(おおたによしつぐ)の娘である「竹林院」(ちくりんいん)を正妻に、兄の「真田信幸」(さなだのぶゆき:真田信之)は徳川方の武将、「本多忠勝」(ほんだただかつ)の娘である「小松姫」(こまつひめ)別名「稲姫」(いなひめ)を正妻としていました。
当時の武士の考え方では、婚姻関係を結んだ一族との義理は非常に重要。一方で当然ながら家や家族、部下を守るのも武士の役目でした。あちらを立てればこちらが立たず、板挟みの状態に悩んだ真田信幸は、自分が徳川方に付き、父・真田昌幸と弟・真田信繫に豊臣方に付くように提案します。どちら側が勝っても負けた側の処罰に対して減刑の嘆願をすることで、主君に尽くすという武士道精神に則りつつ、家族も守るという難問をクリアしようとしたのです。
事実、関ヶ原の戦いは徳川方の勝利で終わりますが、真田信幸の嘆願により真田昌幸・真田信繫親子の死刑は回避され、2人は流罪となりました。
日本一の兵。義によって戦った真田幸村

真田幸村(真田信繁)は自分の部隊に
赤い鎧を着せて結束を意識付けた
九度山(現在の和歌山県)に配流された真田信繫は約14年をこの地で過ごします。そのあいだに父である真田昌幸を亡くしますが、本人は子宝に恵まれるなど、貧しいながらも穏やかな暮らしが続きました。
しかし、徳川氏と豊臣氏の関係が悪化した1614年(慶長19年)に豊臣の家臣として戦って欲しいとの要望を受けると、真田幸村を名乗り、息子の「真田大助」を伴い大坂城(現在の大阪城)へ入場したのです。
籠城戦を行うという方針が決定すると、真田幸村は大坂城内に攻防一体の出城「真田丸」(さなだまる)を建設。戦闘がはじまると、父の真田昌幸も得意とした、敵を自陣へ引き込んでから打ち倒す戦法で大きな戦果を挙げます。その数日後には両陣営による和議が成立。圧倒的不利とみられていた豊臣方が、徳川との和議にこぎ付けられたのは、真田幸村の奮戦も大きな理由になりました。
この活躍を見た徳川家康は真田幸村に対し、徳川方へ寝返るように使者を出しますが、豊臣に対する忠義を貫いた真田幸村はこれを拒否。半年後の大坂夏の陣にも参戦し、そのさなかで討死することになります。
大河ドラマ真田丸はこれらの史実に加え、当時最新の研究結果であった「真田信繫は豊臣秀吉の馬廻衆[うままわりしゅう:大将の馬の周りで護衛や伝令を行う親衛隊]だった」という一説を反映されています。また、真田幸村という名前の命名方法や、真田幸村の最期などドラマ独自の演出も多彩に導入。家族愛と武士の矜持を随所に感じられる名作となりました。
龍馬伝
幕末の風雲児、坂本龍馬を描いたオンリーワンの名作
「龍馬伝」は2010年(平成22年)に放送された、49作の大河ドラマです。主人公の「坂本龍馬」を演じた「福山雅治」(ふくやままさはる)さん。俳優でありミュージシャンでもある福山雅治さんは、劇中にて実際に三味線を演奏するなど、彼にしかできない坂本龍馬を演じて話題を呼びました。
また、史実では海援隊組織後に出会う「岩崎弥太郎」(いわさきやたろう)が幼少期からの知己であったというオリジナルの設定も特徴的。本作品は岩崎弥太郎の視点で描かれた坂本龍馬をコンセプトにしたドラマになっています。
坂本龍馬と武士道
貧弱な坂本龍馬が「武士」になれたのは姉のおかげ?
坂本龍馬は土佐藩(現在の高知県)の下級武士の家に生まれました。幼少期は貧弱で甘えん坊だった坂本龍馬ですが、姉の「坂本乙女」(さかもとおとめ)に鍛えられ、10代後半には武芸を修める立派な青年に成長します。坂本龍馬のなかの武士としての心得、武士道の学びは、姉がいなくては成り立たなかったと言えるでしょう。
剣術修行のために江戸と土佐を行き来するようになった坂本龍馬は、出会った人々や黒船の来航といったできごとに影響され、海外に興味を持ちはじめるようになりました。
一方で坂本龍馬が属する土佐藩内部は、上級武士と下級武士の考え方の違いが理由で対立。尊王攘夷を主張する下級武士からは、脱藩する人物も現れはじめます。坂本龍馬も周囲の人間の誘いを受ける形で脱藩。紆余曲折を経て、もう一度江戸へ入りました。
脱藩は、連帯責任で家族まで罰せられるほどの重罪であり、このときの坂本龍馬にはそれほどのリスクを背負ってでも日本のために行動しようとした覚悟があったと言えます。
勝海舟との運命的な出会い
倒幕のため、新しい時代のために奔走した坂本龍馬

江戸時代までとは違う
幕末武士道の体現者、坂本龍馬
勝海舟のもとで国際情勢や軍艦の運用法などを勉強していた坂本龍馬は脱藩から3年後の1865年(慶応元年)、「亀山社中」(かめやましゃちゅう)という組織を結成。のちに海援隊と名を改められるこの組織は、貿易業を中心にした現在の株式会社のようなシステムを有し、水面下では政治活動も行っていました。
坂本龍馬がこのような組織を興した背景には、倒幕のために必要な力を有していた薩摩藩と長州藩を結束させる狙いがあったのです。当時両藩は方針の違いから対立していましたが、坂本龍馬や勝海舟、「中岡慎太郎」(なかおかしんたろう)らの必死の説得により足並みをそろえることを了承。薩長同盟が締結されました。
この薩長同盟を発端に討幕運動が活性化すると、1867年(慶応3年)に「徳川慶喜」(とくがわよしのぶ)による大政奉還が成立。260年に亘った江戸幕府による政権は終わりを告げ、坂本龍馬が夢見た新しい時代がやってくるのでした。
その1ヵ月後、坂本龍馬は京都で暗殺され33歳という若さでその生涯を終えてしまいますが、彼の残した功績は大きく、そのあとの日本の礎となったと言っても過言ではありません。
激動の時代を生きた坂本龍馬の武士道
それまでの時代から受け継がれてきた武士道は、一般的に主君に忠義を尽くすものでした。しかし坂本龍馬の行動は、一見するとその考えに背いているようにも思えます。ですが、坂本龍馬は「日本」という主君を守るためにはどうすれば良いか、日本に生きる「人」のためになにをすれば良いかを重要視し、一貫して行動していました。
そのためには古い体制を壊すこともやむなしという覚悟と信念。これこそが坂本龍馬の、そして幕末志士達の武士道と言えるのではないでしょうか。