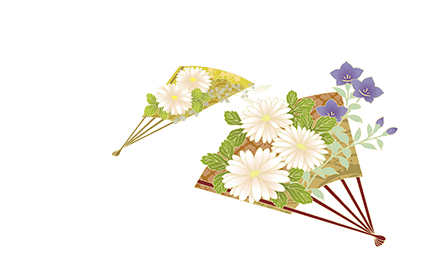鎌倉9代将軍を一覧にしました。鎌倉時代は約150年続いた時代。「源頼朝」(みなもとのよりとも)による鎌倉幕府の樹立に始まり、「承久の乱」、「元寇」(文永の役・弘安の役)などを経て、96代「後醍醐天皇」(ごだいごてんのう)らに倒されました。そんな鎌倉幕府のトップに立っていたのが「将軍」です。しかし源頼朝の死後、実際は北条氏を中心とする「執権」が実権を握っていたのも鎌倉時代の特徴と言えます。
「鎌倉9代将軍」は、源頼朝から最後の鎌倉幕府将軍「守邦親王」(もりくにしんのう)まで、9人の将軍について学ぶのにピッタリのコンテンツ。気になる人物を選択すると、その人物の生涯を詳しく知ることができます。歴史の勉強・学び直しにもおすすめです。
日本ではじめて「幕府」という統治機構を作り出した「源頼朝」。罪人として伊豆国(いずのくに:現在の静岡県伊豆半島)に流されながらも、宿敵である平氏一族の打倒に成功し、鎌倉幕府初代将軍に就任しました。しかし、実際の戦いは、ほとんど弟達に任せ、自身は政権基盤の構築に注力。日本史上を振り返っても、政治に特化して天下草創を成し遂げた人物は極めて稀です。果たして源頼朝は、どのようにして鎌倉幕府の創設を実現したのでしょうか。源頼朝の巧みな政治手腕を軸に、波瀾万丈の生涯を紹介します。源頼朝の政治 YouTube動画
鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」(みなもとのよりとも)の嫡男として、鎌倉幕府2代将軍を務めたのが、「源頼家」(みなもとのよりいえ)です。弱冠18歳で父の跡を継いだものの、早々に有力御家人衆による「13人の合議制」が敷かれたことで実権を剥奪され、政争の渦中へと身を投じることになってしまいました。なぜ、源頼家は御家人達の統制に失敗し、非業の死を遂げることになったのでしょうか。鎌倉に巻き起こった政争をひも解きながら、その生涯をたどります。
鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」(みなもとのよりとも)の次男として生まれ、兄である鎌倉幕府2代将軍「源頼家」(みなもとのよりいえ)の失脚によって、鎌倉幕府3代将軍を継いだのが「源実朝」(みなもとのさねとも)です。しかし、就任早々、北条氏に実権を奪われると徐々に政治から遠ざかり、和歌などの趣味の世界に没頭するようになりました。その歌人としての才能は極めて高く、百人一首に選ばれた他、のちに「金槐和歌集」(きんかいわかしゅう)も残しています。ところが、予期せぬ暗殺事件によって源実朝は落命。これによって清和源氏の嫡流は断絶してしまいます。源実朝は、なぜ政治から離れ、そして暗殺されなければならなかったのでしょうか。生涯を振り返りながら、その背景をひも解いていきます。
鎌倉幕府史上、はじめて清和源氏の嫡流以外から鎌倉幕府将軍に立てられ、鎌倉幕府4代将軍を継いだのが、「藤原頼経」(ふじわらのよりつね)です。公家の頂点に立つ摂家(せっけ:天皇の補佐職である摂政と関白を輩出した藤原一族)のひとつ、「九条家」(くじょうけ)出身だったことから「摂家将軍」(せっけしょうぐん)と称されましたが、実態は執権を担う北条家の傀儡(かいらい:操り人形)に過ぎませんでした。ところが、反執権勢力が藤原頼経に接近したことで状況が変化。鎌倉幕府内において一定の勢力を保持するようになり、やがて北条家より、鎌倉幕府将軍の譲位(位を譲ること)を申し付けられました。北条家との関係に注目しながら、藤原頼経の生涯を紹介。譲位に至った経緯についても解明していきます。
鎌倉幕府4代将軍を務めた父「藤原頼経」(ふじわらのよりつね)の追放により、わずか6歳で鎌倉幕府5代将軍に就任したのが、「藤原頼嗣」(ふじわらのよりつぐ)です。「摂家」(せっけ:天皇を補佐する摂政と関白を輩出した藤原一族)のひとつ「九条家」(くじょうけ)の血を引くため、父同様「摂家将軍」(せっけしょうぐん)と称されました。しかし、鎌倉幕府将軍の在位はわずか8年間。執権を担う北条得宗家(北条家嫡流)と親密な関係を築いていたものの、「大殿」(おおとの)として君臨した父・藤原頼経の暗躍、反得宗家勢力による謀反の企てに巻き込まれ、失脚することになるのです。いったい背景には何があったのでしょうか。藤原頼嗣の生涯とともに、鎌倉幕府将軍の更迭に至った経緯などをひも解きます。
鎌倉幕府6代将軍「宗尊親王」(むねたかしんのう)は、鎌倉幕府史上初の「皇族将軍」(こうぞくしょうぐん)として知られています。88代「後嵯峨天皇」(ごさがてんのう)の皇子であり、皇位継承候補のひとりでしたが、朝廷内の事情と執権を担う北条得宗家(北条家の嫡流)の思惑が絡み合い、わずか11歳で鎌倉幕府将軍に就任。政権とは無縁のまま、和歌に没頭する日々を過ごしました。ところが、鎌倉幕府将軍の在位14年を経た頃、突如として鎌倉幕府将軍を解任。京へと送還されてしまいます。宗尊親王はなぜ、失脚の憂き目に遭ったのでしょうか。生涯をたどりながら、その理由を探ります。
未曾有の国難として知られる「元寇」(げんこう)が起こったとき、鎌倉幕府7代将軍を務めていたのが「惟康親王」(これやすしんのう)です。無論、政権は握っておらず対処はすべて8代執権「北条時宗」(ほうじょうときむね)が主導。しかし、惟康親王にも役割が与えられました。鎌倉幕府将軍の権威を示すために、源氏の姓を名乗るよう指示されたのです。つまり、象徴として存在することだけが、惟康親王の価値でした。元寇のあとも、北条得宗家(北条家の嫡流)の意向に寄り添いながら、鎌倉幕府将軍という役割を忠実に担い続けた惟康親王ですが、やがて解任されて、京へ追放。歴代の「摂家将軍」(せっけしょうぐん)、「皇族将軍」(こうぞくしょうぐん)同様の末路をたどりました。北条得宗家との関係に注目しながら、惟康親王の生涯を解説。鎌倉幕府将軍就任から元寇、そして鎌倉幕府将軍の解任に至るまでの軌跡を見ていきます。
鎌倉幕府8代将軍「久明親王」(ひさあきらしんのう)は、朝廷内で起こった「皇統」(こうとう:天皇の血統)の分裂が引き金となって誕生した、「皇族将軍」(こうぞくしょうぐん)です。鎌倉幕府において実権を持たず、与えられた役割はあくまで北条得宗家(ほうじょうとくそうけ:北条家の嫡流)の傀儡(かいらい:操り人形)。そのため、和歌に没頭する日々を過ごし、「鎌倉歌壇」(かまくらかだん)を代表する歌人としてその名を馳せました。しかし、歴代の鎌倉幕府将軍とは決定的に異なる点があり、それは鎌倉幕府将軍の退位が平穏に行われた、はじめての人物でした。いったいなぜ、北条得宗家と良好な関係を保ち続けることができたのでしょうか。久明親王の生涯とともに、その理由を探ります。
最後の鎌倉幕府将軍として知られるのが、「守邦親王」(もりくにしんのう)です。わずか8歳で、鎌倉幕府9代将軍を継ぎますが、実権は北条得宗家(ほうじょうとくそうけ:北条家の嫡流)によって牛耳られ、表舞台に現れることはほとんどありませんでした。鎌倉幕府滅亡のときでさえ、存在感は希薄。倒幕軍からは、打倒すべき敵とすら認識されていなかったのです。鎌倉幕府の崩壊までの経緯とともに、守邦親王の生涯を解説。鎌倉幕府将軍でありながら、最後まで敵味方双方から軽んじられた背景をひも解きます。