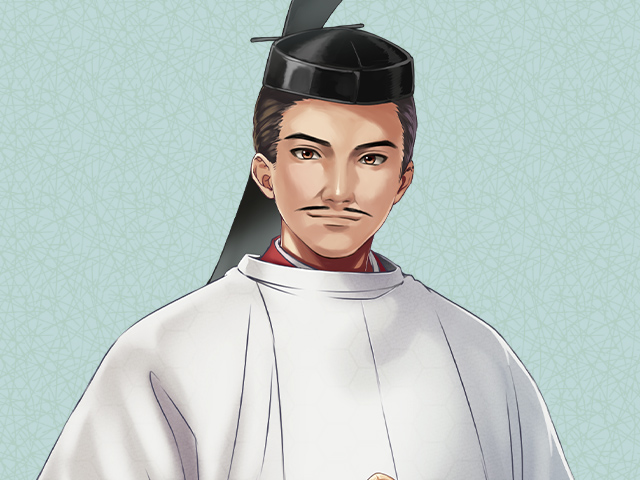徳川家康 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
徳川家康の生涯
織田家・今川家の人質だった幼少期

徳川家康
1542年(天文11年)12月26日、徳川家康は松平宗家8代当主「松平広忠」(まつだいらひろただ)の嫡男として「岡崎城」(愛知県岡崎市)にて生を受けました。母は「於大の方」(おだいのかた:のちの伝通院[でんづういん])。幼名は「竹千代」(たけちよ)です。
竹千代(徳川家康)が生まれた当時の三河国(現在の愛知県東部)は、遠江国(現在の静岡県西部)・駿河国(現在の静岡県中部)を領する「今川義元」(いまがわよしもと)と、尾張国(現在の愛知県西部)の「織田信秀」(おだのぶひで:織田信長の父)という強者に挟まれている状況でした。
そうした中、竹千代は数え6歳のときに今川家の人質として駿府(現在の静岡県静岡市)へ送られることとなります。ところが、駿府への護送の途中で家臣が裏切り、尾張国の織田信秀のもとへ送られてしまうのです。
そのまま織田家の人質として留め置かれることになった竹千代でしたが、1549年(天文18年)に父・松平広忠が死去すると、織田家・今川家の人質交換によって今川義元のもとへと移されます。
竹千代は、今川義元の後見で14歳のときに元服しました。今川義元から「元」の一字をもらい、名を「松平元信」(まつだいらもとのぶ)とし、そのあと、「松平元康」(まつだいらもとやす)へと改名。また、今川義元の姪とされる「築山殿」(つきやまどの)を正室に迎えています。
「桶狭間の戦い」ののち今川家から独立

岡崎城
1560年(永禄3年)に今川義元が尾張国へ侵攻した「桶狭間の戦い」では、松平元康(徳川家康)は「大高城」(名古屋市緑区)へ兵糧を運び込む先鋒を任され完遂するものの、今川義元が織田軍に討たれたという一報を受け取ることになりました。
松平元康は、一旦松平家の菩提寺である「大樹寺」(愛知県岡崎市)へ入り、岡崎城にいた今川軍の残兵が退去するのを待って岡崎城へ入城します。今川家から独立した松平元康は、1562年(永禄5年)に織田信長と軍事同盟である「清洲同盟」を結びました。さらに、今川家からの独立を明確にするという意図もあり、1563年(永禄6年)には名前を「家康」に改めます。
1564年(永禄7年)、「三河一向一揆」が勃発するも、これを鎮圧し、さらに敵対勢力を退けて東三河・西三河を平定。三河国を統一しました。1566年(永禄9年)には、朝廷から「従五位下三河守」(じゅごいのげみかわのかみ)に叙任され、姓も「松平」から「徳川」へと改名しています。
本拠地を岡崎から浜松へ移す
大敗北を喫した「三方ヶ原の戦い」

武田信玄
徳川家康は、1572年(元亀3年)に生涯最大の負け戦を経験します。甲斐国(現在の山梨県)の「武田信玄」は、「西上作戦」と呼ばれる遠江国・三河国への侵攻を開始。「二俣城」(静岡県浜松市天竜区)を陥落させます。徳川家康は、武田信玄の狙いは浜松城であると予想し、織田信長から送られた援軍と合わせて約11,000の兵で浜松城に籠城することとしました。
ところが、浜松城へ近付いた武田軍は、浜松城への進路から逸れ、三河国へ向かうような動きを見せたのです。戦国時代、行軍の先にある城を攻めないというのは通常、考えられない事態でした。
徳川方の重臣達は、これは武田信玄の挑発行為であるから乗ってはいけないと引き留めるものの、徳川家康は武田軍の背後から狙うことを決断します。
重臣らが懸念した通り、30,000とも言われる武田軍はすでに陣形を整えて待ち構えていました。徳川家康の軍も果敢に戦いましたが、圧倒的戦力を有する戦巧者の武田信玄には敵わず惨敗を喫してしまいます。徳川家康は辛くも浜松城まで逃げ帰りました。その間、徳川家康を守るために多くの家臣が戦死したと伝えられているのです。
徳川軍を撃退した武田軍は進軍を再開しますが、三河国の「野田城」(愛知県新城市)を落としたあと、武田信玄が病を発して後退。1573年(元亀4年)に武田信玄が病没したことで武田軍は撤退しています。
「長篠の戦い」に勝利するも家族には悲劇が!

武田勝頼
武田信玄が病没したために、織田信長に敵対する勢力による「信長包囲網」が瓦解し、徳川家康も勢力を回復。武田家から奥三河を奪還し、駿河国の武田領にまで迫ると、武田信玄の跡を継いだ「武田勝頼」(たけだかつより)と攻防を繰り返します。
1575年(天正3年)の「長篠の戦い」では、織田・徳川連合軍が武田軍を破り、この勢いに乗じて武田軍に奪われていた二俣城、「諏訪原城」(静岡県島田市)など遠江国の要衝となる城を奪取した徳川家康は武田家の優位に立ちました。
その後の1579年(天正7年)頃、徳川家に悲劇的なできごとが起こります。織田信長から正室・築山殿と嫡男・松平信康に対して武田家への内通疑惑がかけられたのです。徳川家康は織田信長と談判しますが、結果的には織田信長との同盟関係維持を第一として、築山殿を殺害、松平信康は切腹させることになります。
「神君伊賀越え」で危機を突破

明智光秀
1582年(天正10年)5月21日、徳川家康は元武田家臣の「穴山信君」(あなやまのぶただ)とともに、織田信長の居城「安土城」(滋賀県近江八幡市)を訪れ接待を受けました。
このあと、堺(現在の大阪府堺市)を遊覧中だった徳川家康は、1582年(天正10年)6月2日に「本能寺の変」が起こったことを知ります。織田信長が少人数で京の「本能寺」(京都市中京区)に滞在しているとき、重臣の「明智光秀」(あけちみつひで)が謀反を起こして織田信長を襲撃したのです。
徳川家康も少数の供しか連れておらず、明智軍に狙われるという危険な状況にありました。そこで家臣達の進言を聞き入れ、街道を避けて伊賀国(現在の三重県伊賀市)の山道を越え、伊勢国(現在の三重県北中部)から海路で三河国へ戻る経路を選択します。のちに「神君伊賀越え」と呼ばれる逃亡劇により、徳川家康は無事に三河国へ帰還しますが、別の経路を選んだ穴山信君は途中で命を落としました。
豊臣秀吉との唯一の武力衝突「小牧・長久手の戦い」
織田政権内で影響力を増した豊臣秀吉は、織田信長の次男「織田信雄」(おだのぶかつ)と手を結び、織田家筆頭家老であった「柴田勝家」(しばたかついえ)を「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)で打ち破ります。
ところが、豊臣秀吉が織田信長の嫡孫「三法師」(さんぽうし:のちの織田秀信[おだひでのぶ])を押し戴くようになると、織田信雄は豊臣秀吉と対立して徳川家康に接近。1584年(天正12年)には、織田信雄・徳川家康軍と豊臣秀吉軍が相対する「小牧・長久手の戦い」へと発展しました。
全面的な衝突にはならなかったものの、局地的な戦いでは徳川家康軍が勝利。しかし、豊臣秀吉から講和を持ちかけられた織田信雄がこれを受けたため、織田信雄を支援するという名目で参戦していた徳川家康は戦う理由を失い、三河国へと帰還したのです。
そして1586年(天正14年)頃から、豊臣秀吉は徳川家康に臣従するよう求めるようになります。臣従を拒否する徳川家康に対して、豊臣秀吉は実妹の「朝日姫」(あさひひめ:旭姫とも)を継室として輿入れさせ義兄弟となった他、母の「なか」(大政所[おおまんどころ]とも)を朝日姫の見舞いと称して岡崎へ送りました。
「小田原征伐」後、徳川家康は関東へ移封
1590年(天正18年)、豊臣秀吉は大名同士の私闘を禁じた「惣無事令」(そうぶじれい)に違反したとして北条氏討伐を実行します。
徳川家康もこの「小田原征伐」で先鋒を務め、北条氏が降伏したのち、豊臣秀吉の命令で北条氏の旧領であった関東へ移封。生国である三河国から離れることとなりましたが、移封先の関東では武蔵国「江戸城」(東京都千代田区)を居城として、江戸の町の開発と整備に力を注ぎます。また、小規模だった江戸城には本丸、二の丸などを増築し、大規模な改修を行いました。
豊臣秀吉が徳川家康を関東へ移封した狙いはその力を削ぐためでしたが、徳川家康は旧武田家臣や北条氏の家臣を迎え入れ、軍事力の増強に努めるとともに、関東での支配力を強化していったのです。豊臣秀吉にとっては狙いが裏目に出る結果となりました。
豊臣秀吉亡きあとの「関ヶ原の戦い」

関ヶ原古戦場
1598年(慶長3年)、病床にあった豊臣秀吉は、嫡男「豊臣秀頼」(とよとみひでより)が成人するまで政権運営を担うための「五大老」と「五奉行」を任命。1598年(慶長3年)8月18日に豊臣秀吉が病没すると、五大老の筆頭である徳川家康は、豊臣政権内で徐々に実権を握るようになります。徳川家康は、豊臣秀吉が遺言により禁止した諸大名同士の婚姻や、武士の給料である禄高の増減に関与することなどを行っていきました。
こうした徳川家康の行いに反感を募らせ行動を起こしたのが五奉行筆頭の「石田三成」(いしだみつなり)です。1600年(慶長5年)、会津(現在の福島県西部)の「上杉景勝」(うえすぎかげかつ)に謀反の疑いありとして、徳川家康は兵を挙げ会津に向かいます。
これを好機と捉えて、徳川家康に反対する石田三成と諸大名からなる西軍が挙兵しました。「会津征伐」の途上で石田三成挙兵の一報を受けた徳川家康は、進軍を取りやめ、石田三成に反感を持つ諸大名を招集して東軍を結成。1600年(慶長5年)9月15日に美濃国不破郡関ヶ原(現在の岐阜県不破郡関ケ原町)を主戦場として東軍と西軍が激突します。
開戦当初は西軍が優勢だったと言われていますが、次第に西軍から東軍へ寝返る大名が出はじめ形勢が逆転。これは、事前に徳川家康が諸大名に対して手紙を送り、根回ししていたことが功を奏したと考えられています。天下分け目の「関ヶ原の戦い」は、およそ6時間後に東軍の勝利で終結しました。
徳川家にとって危険な豊臣家を滅ぼす
1603年(慶長8年)、徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任命され、江戸幕府が開かれます。しかし、徳川家康が江戸幕府将軍の地位に就いていた期間は短く、1605年(慶長10年)には将軍職を三男の「徳川秀忠」(とくがわひでただ)に譲り、自らは「駿府城」(静岡県静岡市)へ移転。表舞台からは一歩引いたものの、大御所として権勢を維持していました。
江戸幕府を開いた徳川家康でしたがなおも懸念材料があり、それは大坂でいまだ影響力を持つ豊臣家です。徳川家康が豊臣家に対する不安を完全に払拭できたのは、1614年(慶長19年)の「大坂冬の陣」と1615年(慶長20年)の「大坂夏の陣」に勝利したときでした。

現在の大阪城
大坂冬の陣では、豊臣方と和睦した徳川家康は、大坂城の外堀から二の丸、三の丸までは破壊して埋め立て、本丸のみを残す無防備な状態にしています。そして大坂夏の陣で徳川家康は完全勝利を収め、豊臣秀頼とその母「淀殿」(よどどの:茶々とも)は自害。大坂城は焼け落ちて、豊臣宗家は滅亡しました。この勝利をもって徳川家康の天下掌握は達成されたのです。
徳川家康は若い頃から晩年まで健康に留意した生活を続け、大坂夏の陣の翌年1616年(元和2年)に75歳でその生涯を閉じました。
徳川家康と豊臣兄弟の逸話
徳川家康と豊臣秀吉による腹のさぐりあい
徳川家康と豊臣兄弟は、同じ時代に織田信長に従い、織田信長亡きあとには味方にも好敵手にもなった間柄です。とは言え、徳川家康と豊臣兄弟の弟・豊臣秀長がかかわった逸話はあまり多くはありません。
一方の豊臣秀吉に対しては、徳川家康が正面から武力衝突したのは小牧・長久手の戦いのみで、それ以外では水面下での駆け引きが繰り返されました。

徳川秀忠
1590年(天正18年)、小田原征伐が行われようとしていたときのこと。徳川家康は、まだ子どもだった三男の徳川秀忠を豊臣秀吉のもとへと向かわせます。お供には「井伊直政」(いいなおまさ)ら重臣が付きました。名目は跡継ぎ候補の上洛でしたが、実質的には、小田原征伐で諸大名が裏切らないよう担保とする人質です。
ところが豊臣秀吉は謁見を終えると、徳川秀忠を供の者ともどもあっさり帰します。
徳川家康は喜んだものの、これには裏があり、豊臣秀吉は徳川家康に何か要求してくるに違いないと気付きました。そしてそれは、小田原征伐に際して徳川領内の諸城を使いたいという要求であろうと読んだ徳川家康は、重臣の「本多正信」(ほんだまさのぶ)に命じて三河国から東の諸城を修築させ、さらには道路や橋の修繕も行わせます。
実際に徳川家康の読み通り、小田原征伐では豊臣秀吉から徳川領内の城を借りたいという要請があったとのこと。徳川家康は準備万端整えた上で、豊臣秀吉に城を貸すことができたのです。
豊臣秀吉が「上から目線」で1本!
徳川家康と豊臣秀吉の駆け引きには、豊臣秀吉が1本取った小さな逸話もあります。徳川秀忠が上洛して、はじめて豊臣秀吉に謁見したとき、豊臣秀吉の母・なかが徳川秀忠の髪を結ったり、着替えさせたりしていました。
豊臣秀吉は、お供の井伊直政らに対して徳川秀忠の人柄をほめたあと、「ただ髪の結い方から、装いまですべてが田舎びているので、京風に改めてお返しします」と伝えたことが歴史書の「徳川実紀」(とくがわじっき)に記されているのです。
豊臣秀吉は親切そうに見せて、「徳川の者は垢抜けていない」と皮肉ったのでした。