豊臣兄弟ゆかりの城・長浜城とは - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
長浜城とは
城の歴史

長浜城址
「長浜城」(現在の滋賀県長浜市)とは、1573年(天正元年)に、豊臣秀吉が新しく築いた城のことです。豊臣秀吉にとって、はじめての持ち城で、出世城とも呼ばれています。
長浜城のある北近江国(きたおうみのくに:現在の滋賀県長浜市、米原市、彦根市周辺)は、もともとが浅井長政の領地でした。
しかし、浅井長政は、義兄・織田信長と対立。1570年(元亀元年)に「姉川の戦い」が起こり、浅井長政・朝倉義景連合軍は、織田信長・「徳川家康」連合軍に敗北してしまうのです。浅井長政は、居城「小谷城」(おだにじょう:現在の滋賀県長浜市)へと逃げ帰りましたが、小谷城は織田信長軍が包囲。織田信長軍の豊臣秀吉に降伏を勧められましたが、1573年(天正元年)、浅井長政は自害し、浅井氏は滅亡しました。
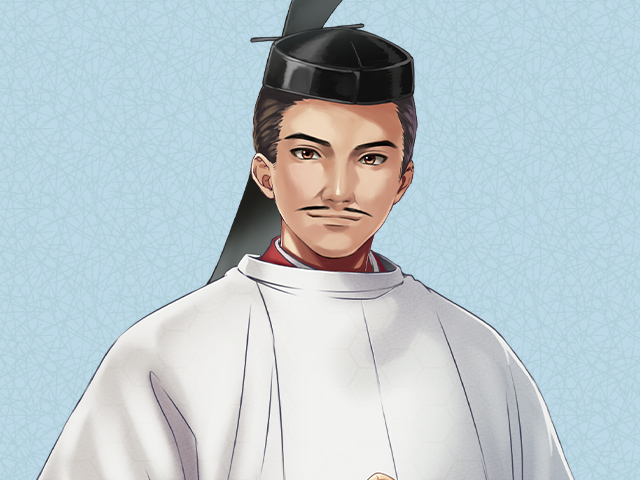
豊臣秀吉
なお、朝倉義景も自害して朝倉氏も滅亡。この一連の戦功により、豊臣秀吉は、織田信長から浅井氏の旧領のうち、120,000石を拝領したのです。豊臣秀吉は「今浜」と呼ばれていた土地を、織田信長の名前から一字取って「長浜」と改め、長浜城を新築し、城下町を形成。なお、浅井長政が居城とした小谷城は廃城とし、小谷城を解体した資材が長浜城の築城に用いられました。
ところが、1582年(天正10年)に「本能寺の変」が勃発し、織田信長が死去。「清洲会議」による話し合いで、長浜城は「柴田勝家」(しばたかついえ)に譲り渡すことになります。しかし、豊臣秀吉と柴田勝家は対立し、「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)となるのです。その結果、豊臣秀吉が勝利。豊臣秀吉は、長浜城を取り返し、「山内一豊」(やまのうちかずとよ)に与えます。その後「内藤信成」(ないとうのぶなり)、「内藤信正」(ないとうのぶまさ)親子が入城しましたが、1615年(元和元年)に廃城となりました。
なお、長浜城は解体されて、「彦根城」(ひこねじょう:現在の滋賀県彦根市)に移築。また、大手門(おおてもん:正門)は長浜市内の「長浜別院大通寺」(ながはまべついんだいつうじ)の台所門に、搦手門(からめてもん:うらもん)は同市内の「知善院」(ちぜんいん)の表門として移築され、現存しています。
長浜城の特徴と見どころ
琵琶湖にせり出た水城

長浜城、安土城、坂本城、大溝城
長浜城の特徴と見どころは、琵琶湖にせり出た水城というところです。城内から水門を通って、琵琶湖に船の出入りができるようになっていたと言われています。
湖畔の美しい城であったことはもちろん、交通や物流がとても便利。例えば、長浜城から「安土城」(あづちじょう:現在の滋賀県近江八幡市)までは約33㎞で、陸上では徒歩で約7時間かかりますが、水上で船に乗れば約1時間で移動可能でした。
これにより、安土城(織田信長の居城)、「坂本城」(さかもとじょう:明智光秀[あけちみつひで]の居城:現在の滋賀県大津市)、「大溝城」(おおみぞじょう:織田信澄[おだのぶずみ]の居城:現在の滋賀県高島市)、長浜城の4城で、琵琶湖沿いを支配。織田信長軍が支配する琵琶湖を通らなければ、京への行き来はできないようになったのです。豊臣秀吉にとっては、織田信長に何かあれば、すぐに駆け付けることができる位置。長浜城は、まさに豊臣秀吉が、織田信長への忠誠心を示して建てた城と言えるのです。
長浜城歴史博物館
長浜城の逸話
石田三成と出会う

石田三成
長浜城主となった豊臣秀吉の逸話として、有名なのが「三献茶」(さんけんちゃ)の話です。
1574年(天正2年)、豊臣秀吉は長浜城から鷹狩りに出掛け、途中で「大原観音寺」(おおはらかんのんじ:正式名称は伊富貴山観音護国寺[いぶきやまかんのんごこくじ]、現在の滋賀県米原市)に立ち寄りました。そこで出会ったのが、「石田三成」(いしだみつなり)です。
豊臣秀吉が、お茶を所望したところ、すぐに少年・石田三成がぬるめのお茶を提供。鷹狩りで喉が渇ききっていた豊臣秀吉は一気に飲みきり、2杯目を所望します。すると、今度は、やや熱めで量は半分くらいのお茶を提供しました。豊臣秀吉が、3杯目を所望したところ、今度は小さく高価な茶碗に入った、熱いお茶を提供したのです。豊臣秀吉は、その少年の気配りに感心し、才気を見抜いて家臣とし、長浜城に連れ帰ったと言われています。そして、豊臣秀吉の存命中、右腕として活躍したのです。
政所茶

茶葉
「三献茶」として提供されたお茶が、「政所茶」(まんどころちゃ)です。政所茶とは、滋賀県東近江市周辺で、室町時代から約600年、栽培されているお茶のこと。茶摘み歌でも、「宇治は茶所、茶は政所」とあり、朝廷や幕府に献上されるほど、おいしい茶葉として知られていました。苦味の中に甘味がある、風味に富んだ政所茶は、豊臣秀吉のお気に入りのお茶と言われています。



























