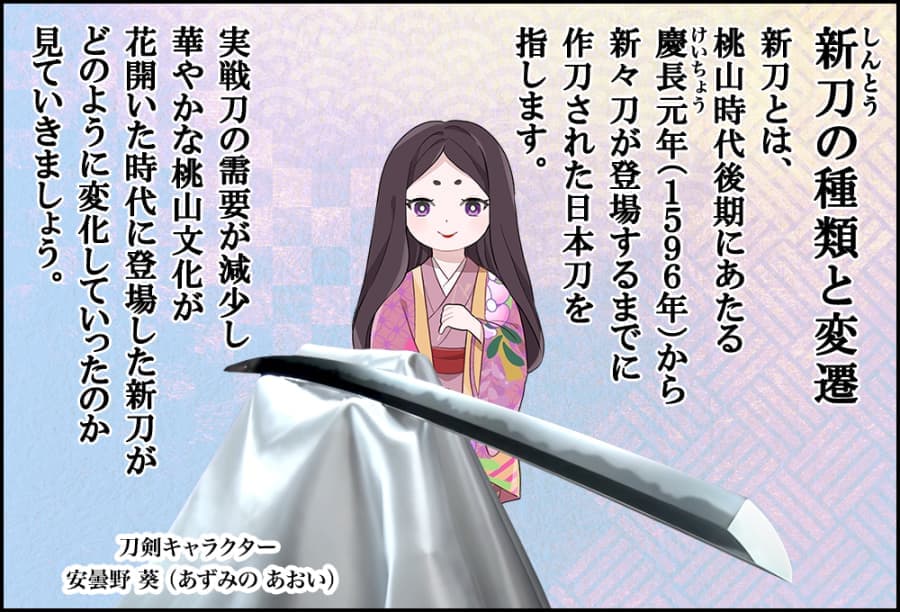第14回「新刀の種類と変遷」
刀剣マンガ教室第14回「新刀の種類と変遷」では、江戸時代初期から江戸時代中期にかけて作刀された日本刀「新刀」について紹介いたします。
街道が整備され、泰平の世となり、人や物の往来がしやすくなった江戸時代を謳歌した期間に作刀された日本刀は、時代を反映するような華やかなものでした。
新刀安土桃山時代末期から江戸時代中期に作刀された「新刀」ついてご紹介します。
新刀の刀工「新刀の刀工」をはじめ、日本刀に関する基礎知識をご紹介します。
慶長新刀慶長新刀が作刀された時代的背景と代表的な刀工にご紹介します。
江戸新刀江戸新刀が作刀された時代的背景と代表的な刀工にご紹介します。
大坂新刀大坂新刀が作刀された時代的背景と代表的な刀工にご紹介します。
寛文新刀寛文新刀が作刀された時代的背景と代表的な刀工にご紹介します。
登場キャラクター
 平安時代の刀剣キャラクター「安曇野 葵」をご紹介します。
平安時代の刀剣キャラクター「安曇野 葵」をご紹介します。