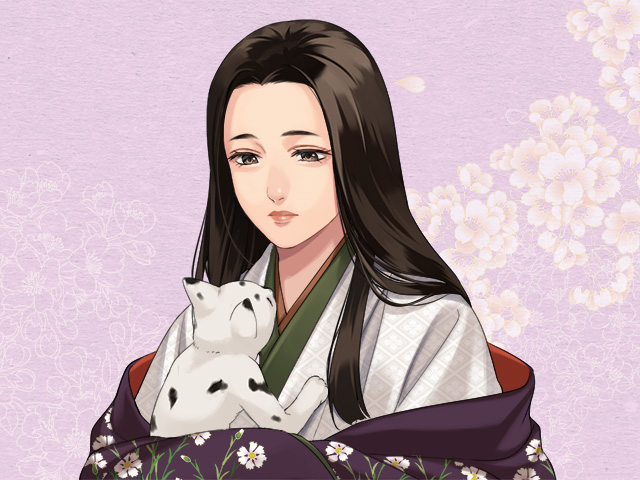小少将の君 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
紫式部の親友・小少将の君とは?
上流貴族の出身だった小少将の君

小少将の君
「小少将の君」は、藤原道長の正妻「源倫子」(みなもとのともこ/りんし)の同母弟「源時通」(みなもとのときみち)の娘として、982年(天元5年)頃に誕生。
しかし父・源時通が出家(しゅっけ:僧籍に入ること)したため、その弟「源扶義」(みなもとのすけのり)の養女となりました。一方で、実は源扶義の娘だったとする説もあります。
小少将の君は、藤原道長夫妻から見れば姪であり、藤原彰子からしてみれば従妹にあたるなど、やんごとない身分の姫君ですが、その出生や幼少期について詳細な記録が残されていないのが現状です。
「小少将の君」という名も藤原彰子に仕えたときの通り名で、実名は伝わっていません。また姉がひとりおり、共に藤原彰子に仕え「大納言の君」(だいなごんのきみ)と呼ばれていました。けれど、小少将の君が女房(にょうぼう:高貴な人々に仕える女性)として宮中で仕え始めた時期も藤原彰子が入内した999年(正歴元年)だったのか、それよりあとだったのか定かではないのです。

藤原彰子
ただ、藤原彰子が1人目の皇子「敦成親王」(あつなりしんのう:のちの後一条天皇[ごいちじょうてんのう])を出産した1008年(寛弘5年)には仕えていたことが「紫式部日記」に記されています。
それも、親などの近親者や長年仕えている女房しか許されない産屋(うぶや:出産時の部屋や建物)の隣室に、小少将の君は控えていました。仕えた年数は不明ながら藤原道長の一族とは血縁関係のため、小少将の君は上臈女房(じょうろうにょうぼう:高位の女官)だったと考えられます。
なお、産屋の隣室には紫式部も同席していました。下級貴族の出身で、藤原一族の血縁者ではない紫式部が居た理由は、おそらく出産時の記録係としてではないかと推測されています。文才を認められていた紫式部だからこその、栄誉ある仕事と言えるでしょう。
共同生活をしていた紫式部と小少将の君
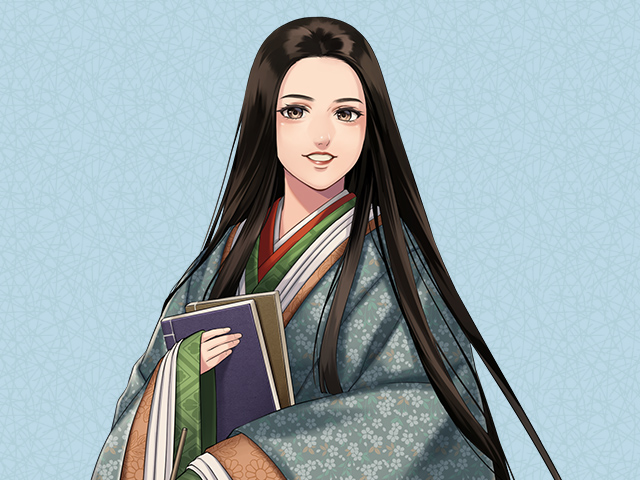
紫式部
人付き合いがあまり得意ではなかった紫式部でしたが、小少将の君とはかなり親しくしていました。それは藤原彰子が、2人目の皇子「敦良親王」(あつながしんのう:のちの後朱雀天皇[ごすざくてんのう])を出産するため実家の土御門邸(つちみかどてい:藤原道長の邸宅)に里下がりした1009年(寛弘6年)のことです。
その際、小少将の君と紫式部といった数人の女房もお供しました。そこで2人は、割り当てられた局(つぼね:女房の部屋)の几帳(きちょう:部屋の仕切り)を取り払って部屋を共有。あまりに仲が良いため、その様子を「男性が忍んで会いに来た場合、お互いに困るのではないか?」と藤原道長に心配されるほどでした。
恋人がいないことを詠み合った贈答歌
「紫式部集」には、小少将の君と紫式部の2人、恋人がいないことを交わし合った贈答歌(ぞうとうか)が収められています。小少将の君が、とある6月7、8日の月がうっすら浮かぶ夕方頃、内裏(だいり:天皇が住み、政務を行う場所。後宮もこの中にあった)で水鳥が鳴く様子を先に詠みました。
<原文>
天の戸の 月の通ひ路 ささねども いかなるかたに たたく水鶏ぞ
<現代語訳>
水鳥が鳴いているわ。まるで殿方が「開けて」と戸を叩く音のよう。私は戸に錠をかけていないのに、いったい誰が叩いているの
紫式部の返歌がこちらです。
<原文>
槙の戸も ささでやすらふ 月影に 何をあかずと たたく水鶏ぞ
<現代語訳>
誰か来るかもしれないと思い、戸を閉めずにためらっているけれど、私の部屋を叩く音なんか聞こえないわ。あの水鳥は、どこの部屋の戸を不満げに叩き続けているのかしら
日が沈みかけた頃に鳴く水鳥を、逢引に訪れた男性に例えた和歌です。どこかの部屋では男性が戸を叩く音がするけれど、私達の部屋ではそんな音はしませんね、と小少将の君と紫式部と語り合っています。
恋人がいようといまいと2人の関係が変わることはなく、なんでも打ち明けることのできた2人。だからこそ、部屋を分ける必要はなかったのです。
小少将の君は、源氏物語に登場する人物のモデルだった?
「紫式部日記」には、藤原彰子に仕える女房達の容姿や装束、性格について批評が記した章があります。そこで紫式部は小少将の君について、「上品で優雅。まるで2月頃の枝垂れ柳のような風情。可愛らしく、とても奥ゆかしい。けれど自分の意志で物事を決めるのが苦手で、人付き合いを恥ずかしがるところといったら、まるで子供のよう。それに、他人に意地悪をされたらすぐに落ち込んでしまいそうな人。あまりにか弱くて、ついつい手を貸したくなる」と多くの言葉で語っているのです。
普段から小少将の君をよく見ていなければ、ここまで詳細な言葉は出てきません。紫式部が小少将の君をとても可愛がっていたことが窺える一節です。
紫式部が小少将の君のことを詠んだ和歌
小少将の君は、おそらく1013年(長和2年)頃に亡くなったと推測されています。30歳前後のことで、当時としても早過ぎる死でした。「紫式部集」には、小少将の君を思って詠んだ和歌があります。
<原文>
たれか世に ながらへて見む 書きとめし 跡は消えせぬ 形見なれども
<現代語訳>
書かれた筆跡は形見になるけれど、私もいつかは死んでしまう身です。そのあとは、いったい誰がこの手紙を後世まで読み継いでくれるのでしょうか
和歌は、生前の小少将の君から送られた手紙を読み返し、紫式部が詠んだとされています。人付き合いが苦手な紫式部にとって、数少ない友人のひとりだった小少将の君を亡くした悲しみは、とても大きかったことでしょう。