光る君へ 7話「おかしきことこそ」 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
あらすじ(2024年2月18日放送分)
盗賊団が入ったその日、花山天皇が寵愛した「藤原忯子」(ふじわらのよしこ、演:井上咲楽[いのうえさくら])がこの世を去ります。花山天皇は、藤原忯子と彼女が身ごもっていた子を一度に亡くし、悲しみにくれました。これを知った藤原兼家は東三条殿に安倍晴明を呼び付け、咎めます。藤原兼家は孫の東宮・懐仁親王の即位を望むため、藤原忯子に皇子を生ませないように安倍晴明に命じていたのです。しかし、藤原兼家に責められた安倍晴明は決して怯むことはありません。そればかりか、「自分を侮れば、右大臣家も危うくなる」と脅しにかかるのでした。
この年の秋、花山天皇は伯父である藤原義懐を参議に取り立てます。円融天皇時代から、蔵人頭(くろうどのとう)を務めていた「藤原実資」(ふじわらのさねすけ、演:秋山竜次[あきやまりゅうじ])をも抜く異例の出世です。藤原兼家を嫌う花山天皇にとって信頼できるのは、藤原義懐とまひろの父・藤原為時だけだと考えるようになっていました。
そんなある日のこと、藤原斉信は、和歌の集いに参加している姫達へ、打毬の試合への招待状を送ります。参加者に藤原道長がいることを知ったまひろは招待を断りました。しかし、心を鍛えるためだと思い直し、招待を受けることに。そして試合当日、まひろが試合観戦のために赴くと、藤原道長の側には、藤原行成の代理で直秀が呼ばれており、思わず驚くのでした。
やがて打毬の試合は、藤原道長らの勝利で幕を閉じます。そして、試合が終了した直後、大雨が降り、源倫子の猫が逃げていきました。まひろは慌てて猫を追いかけていくと、猫がある部屋に入っていく様子が見えます。その部屋からは、姫達を品定めしている男達の声が聞こえ、聞くに堪えなかったまひろは、その場から飛び出してしまうのでした。
ライターのつぶやき「さらにこじれる両片思い」
宮中に潜む不穏の種
まひろの周辺では様々な物事が新たな展開を見せ、好むと好まざるとにかかわらず、まひろもさらに深く巻き込まれていくことになるのが第7話です。
まひろとは因縁浅からぬ散楽(さんがく)の「直秀」(なおひで)と一座の面々が盗賊であることがはっきりと示されます。しかも、大内裏(だいだいり:天皇が住む内裏と、政府の役所が置かれた官庁街)から盗んだ品々を貧しい人々に分け与える義賊です。

花山天皇

藤原兼家
散楽の盗賊一味が暗躍していたその日、「花山天皇」(かざんてんのう)が寵愛する「藤原忯子」(ふじわらのよしこ)が世を去ります。藤原忯子は身ごもっていたため、愛する女性と子供を同時に失った花山天皇の悲しみは一通りではありません。
その一方、東三条殿では「藤原兼家」(ふじわらのかねいえ)と陰陽師である「安倍晴明」(あべのはるあきら)の密談が交わされていました。
藤原兼家は、安倍晴明に腹の子の呪詛を命じたものの、藤原忯子の命まで奪えとは言っていないと詰め寄りますが、安倍晴明は怯むどころか自分を侮れば右大臣の一族とて危うくなると脅し返します。藤原忯子と子供を失った花山天皇は、藤原兼家とその息のかかった者を信頼できなくなり、叔父である「藤原義懐」(ふじわらのよしちか)を取り立てることに。花山天皇の威光を笠に着た藤原義懐のふるまいは尊大で、他の公卿達は不満を募らせていくのです。
自らの心に向き合い悩むまひろ
歌に込められた藤原道長の想い
きな臭さが増してゆく宮中をよそに、まひろは藤原道長に対する自らの気持ちに向き合っていました。
第6話のラストで藤原道長より届けられた文には、「ちはやぶる 神の斎垣も 越えぬべし 恋しき人の 見まくほしさに」としたためられています。その意味は、「私は、越えてはならない神社の垣根も踏み越えてしまいそうです。恋しいあなたにお会いしたくて」。藤原道長は自分の心情をまっすぐまひろへ伝えてきました。
「ちはやぶる」は「神」の枕詞(まくらことば)で、「荒々しい」という意味です。この歌のモデルと思われる作品が「伊勢物語」の中にあり、もとの歌では「恋しき人の」の部分が「大宮人」(おおみやびと:宮中に仕える人)となっていますが、藤原道長は「恋しき人の」とはっきり言い切っています。
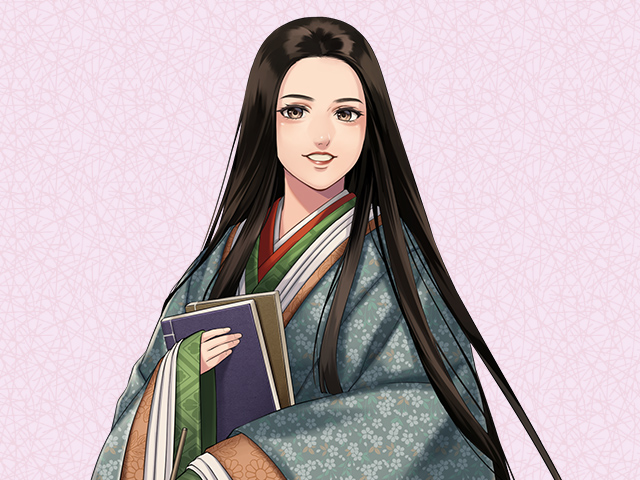
紫式部
また、伊勢物語の歌の原典とされる歌が「万葉集」(まんようしゅう)にあり、そこでは「ちはやぶる 神の斎垣も越えぬべし 今はわが名は 惜しけくも無し」(私は、越えてはならない神社の垣根も踏み越えてしまうだろう。今の私には名も惜しくない)と詠まれています。自分の名よりまひろへの想いの方が大切だと言う藤原道長の強い想いを読み取ることもできるのです。
まひろ、藤原道長の想いから目を背ける
ところが、まひろは藤原道長からの文には返歌を送りませんでした。この段階では、まひろの気持ちははっきりと描写されません。代わりにまひろは、「おかしきことこそ」とつぶやきながら没頭できるものを探すことに。
「おかしきこと」には「興味深いこと」、「滑稽なこと」などの意味があります。「おかし」と言えば、「清少納言」(せいしょうなごん)の「枕草子」(まくらのそうし)を思い浮かべる方も多いと思いますが、「光る君へ」では第6話にて「おかしきことこそめでたけれ」という直秀のセリフが登場しました。
まひろは直秀のいる散楽一座のもとへ出向き、新しい筋書きを提案。以前、「五節の舞」(ごせちのまい)での自分のふるまいを笑いのネタにされそうになったとき、代わりに考えた筋書きは酷評されました。今回は、右大臣家(藤原兼家の一族)の人々を猿に見立て、神のふりをした狐にだまされるというストーリーで、散楽一座が上演すると観客は大喜び。評判になります。
この散楽一座の直秀もいまだ謎の男のままです。ときにはまひろを助けたり、藤原道長にあれこれと忠告したりしますが、盗賊のひとりでもあり、まひろにとって心から信頼できる相手なのかいまだ判然としません。しかも、まひろを憎からず思っているような素振りまで見せることもあり、視聴者にも心の内を読ませないのです。
付かず離れずの両片思い

藤原道長
評判を呼んだ散楽一座の演目でしたが、右大臣家に仕える武士達の耳に入り、怒った武士達と一座の面々は大乱闘に発展。騒ぎを聞き付けた藤原道長が混乱の中からまひろを連れ出し、ふたりはかつて直秀に連れてこられた隠れ家に避難します。
ここでのいっとき、まひろは自分の気持ち、そして藤原道長の想いに向き合おうとしたかのように見えました。ところがすぐに直秀と、まひろの従者の「乙丸」(おとまる)が駆け付けて、まひろは屋敷へ戻ってしまいます。
まひろと藤原道長のいわゆる両片思いはもう少しもだもだが続きそうです。
思いがけない数々の出会い
その後、打毬(だきゅう)の試合が開催されることになり、藤原道長の参加も決まります。打毬とは、馬に乗って毬(まり)を打つ競技で、イギリスで盛んなポロの原型となりました。ペルシャ(現在のイラン)を起源とし、平安時代には日本へ伝わっていたとのことです。まひろは藤原道長も参加すると知り、一旦は観戦には行かないと断言。しかし試合当日になって思い直し、急いで会場へ向かいます。そこではいくつもの驚きがまひろを待っていました。
「源倫子」(みなもとのともこ)らとともに「ききょう」(のちの清少納言)も観戦に訪れていたのです。さらに、馬に乗って入場する藤原道長の組を見れば、直秀もいるではないですか。しかも貴族ではない直秀を仲間に入れるために、「腹違いの弟だ」と嘘までついた藤原道長。腹痛で参加できなくなった「藤原行成」(ふじわらのゆきなり)の代役とは言え、これにはまひろだけでなく視聴者もびっくりです。
身分の差を思い知らされるまひろ
ラストでは、源倫子の猫を追いかけたまひろが知らずに藤原道長達の控室に入ってしまいます。そこでは「藤原斉信」(ふじわらのただのぶ)と「藤原公任」(ふじわらのきんとう)が姫達を勝手に品定めしていました。そしてまひろのことは「地味でつまらない」と評し、女は家柄が大事だと言います。
注意深く聞いていれば、藤原道長が女性に対して身勝手なことは言っていないと分かりますが、男性貴族達の本音を知り、身分の差というものを改めて思い知らされたまひろにその余裕はありません。
たまらずに走り去るまひろの姿を見送ったのは直秀でした。屋敷へ帰ったまひろは、藤原道長の文を蝋燭(ろうそく)の火で燃やして捨てます。
2023年(令和5年)に放送されたNHK大河ドラマ「どうする家康」でも、「大坂夏の陣」を前に「徳川家康」から届いた文に「茶々」(ちゃちゃ)が心を動かされるシーンがありました。しかし茶々も息子「豊臣秀頼」(とよとみひでより)の決意を知ると文を火に投じてしまうのです。文を燃やすという行為には、ただならぬ決意が込められていると感じます。まひろと藤原道長の両片思いはさらにこじれてしまいました。
そして物語は第8回「招かれざる者」へ。まひろの家へ、母の仇である「藤原道兼」(ふじわらのみちかね)が訪れます。まひろはどのような心持ちで対峙するのでしょうか。




























