光る君へ 42話「川辺の誓い」 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
あらすじ(2024年11月3日放送分)
1012年(長和元年)2月、三条天皇は藤原道長の娘・藤原妍子を中宮に、藤原彰子を皇太后にすることを決定します。さらに藤原道長の兄・藤原道綱を「中宮大夫」(ちゅうぐうだいぶ:後宮の事務などを担当する中宮職の長官)に、藤原道長の息子・藤原教通を「中宮権大夫」(ちゅうぐうごんのだいぶ:中宮に仕える役職。中宮大夫の補佐的な役割を持つ)とするよう、藤原道長に命じました。
しかし、その1ヵ月後、三条天皇は、長年付き添った東宮妃の藤原娍子を皇后にすると宣言。藤原道長は、藤原娍子のような後ろ盾のない大納言の息女が皇后になった先例はないと反対しますが、三条天皇は譲りません。その上、藤原道長が聞き入れない場合は、藤原妍子のもとへ渡らないと伝えます。藤原道長は、三条天皇の言葉に抗うことができませんでした。
藤原道長は、すぐに藤原公任、藤原斉信、藤原行成、源俊賢の「四納言」を土御門邸に呼び集め、三条天皇への対抗策を話し合います。そして、藤原娍子の「立后の儀」と藤原妍子の内裏参入を同日に行うことを提案。藤原道長の権力を誇示するために、公卿達が藤原妍子の方へ集まるように仕向けます。
藤原道長の計画を知った三条天皇は、藤原娍子の立后の儀と藤原妍子の内裏参入の時間をずらすことを思い付きました。そうすれば、公卿達はどちらも参加できると考えたからです。しかし、三条天皇の思惑は外れ、立后の儀に公卿達は集まりません。そこで三条天皇は、姿を見せた藤原実資に儀式の「上卿」(しょうけい:儀式などの責任者)を命じます。本来、上卿は右大臣や内大臣が務める役割のため、藤原実資は躊躇しますが、「断られては、藤原娍子が立后できない」と言われ、引き受けるしかありません。こうして、無事に皇后となった藤原娍子ですが、誰も集まらない寂しい席で、三条天皇と自分の行く末に不安を覚えるのでした。
しばらくして、藤原道長は、藤原彰子に呼ばれ、枇杷殿を訪れます。藤原彰子は、藤原妍子が宴三昧で散財してばかりいる、という悪評に心を痛めていたのです。藤原道長は藤原彰子と話したあと、まひろの局を訪ねました。そして、三条天皇が藤原妍子のもとへ渡らないことを伝えると、「一条天皇と藤原彰子の間には、『源氏物語』があった。しかし三条天皇と藤原妍子の間にはなにもない」と悩みを打ち明け、何か良い手立てがないか、問いかけます。しかし、まひろは「物語は人の心を映すが、人は物語のようにはいかない」と答えるのでした。
その後、藤原彰子は、藤原道長に枇杷殿で使う経費を削減することを求めます。また、自分だけではなく、中宮や皇后のかかり(費用)も減らせば、藤原妍子の無駄使いが治まると考えたのです。しかし、藤原道長は、藤原彰子が決めることではないと、突き放すのでした。
藤原彰子のもとを去った藤原道長は、再びまひろの局へ訪れます。しかし、まひろはちょうど実家に戻っており、会うことは叶いませんでした。この夜、藤原道長は、病に倒れてしまいます。
藤原道長の別宅を訪れたまひろは、病にやつれた藤原道長の姿を見て、胸を痛めました。2人は川辺を歩きながら、お互いの気持ちを語り合い、再び共に生きていく決意をします。その後、まひろは藤原道長のために「源氏物語」の執筆を再開するのでした。
ライターのつぶやき「宇治で迎えた人生の転機」
藤原道長の病
死を前にして、まひろと新たな約束を

藤原道長
辞表を提出するほど、重い病に苦しめられた藤原道長は、療養の地を宇治の別荘に移します。そんななか、藤原道長の従者「百舌彦」(もずひこ)がまひろを訪問。万一の場合に備えて、重い病の藤原道長とまひろを会わせたかったようなのです。
そこで、まひろが宇治の別荘を訪れると、藤原道長は柱に寄りかかかって憔悴した様子を見せていました。しかし、まひろの存在に気付いた瞬間、藤原道長は驚きの表情を浮かべて身を動かし、まひろに対する深い愛情を垣間見せたのです。
その後、2人は川辺を歩きます。息子「藤原顕信」(ふじわらのあきのぶ)の出家を嘆き、それを妻「源明子」(みなもとのあきこ)に責められ、自分自身のことすら信じられなくなっている藤原道長の苦悩を知ったまひろは、「この川で2人流されてみません?」と発言。まひろ自身も、「天皇の心を惹き付ける」という「源氏物語」の執筆動機はすでに果たしており、作中で「光源氏」(ひかるげんじ)も亡くなったことから、自分の役目はすでに終わったと感じていました。
しかし藤原道長は、「お前は俺より先に死んではならん」と告げ、まひろも、「道長様が生きておられれば、わたしも生きられます」と対応。まひろの言葉を聞いた藤原道長は、顔を歪めて涙を流します。重責を抱えながらも耐えてきた藤原道長が、弱さを見せた瞬間でした。今回、藤原道長とまひろは「お互いのために生きる」という新たな約束を交わしたのです。
まひろとの約束
「お前との約束を忘れれば、おれの命は終わる」という藤原道長の覚悟の表れのような言葉もありました。強い力を手に入れようとしたのは、20年以上前に、まひろと交わした約束のためだったのです。
その約束は、「直秀」(なおひで)という、共通の友人である義賊の死がきっかけでした。藤原道長は捕まった直秀を助けるために役人に賄賂を渡したのですが、その行動が裏目に出たのか、直秀は殺されてしまったのです。役人が直秀達を殺した本当の理由は明らかにされていませんが、権力をほしいままにしていた藤原摂関家への当て付けだったのかもしれません。自分を責める藤原道長に、まひろは「直秀のような理不尽な殺され方をする人が出ないように、より良き政をする使命がある」と言い、藤原道長は「まひろの望む世をめざす」と告げたのです。
このような悲しい過去があったからこそ、藤原道長は誰にも手出しできない大権力者になろうとしたのかもしれません。しかし、元々の藤原道長は、争いを嫌うおおらかな性格だったので、辛く険しい道であったはず。こののちまひろは、源氏物語の続編「宇治十帖」(うじじゅうじょう)を書き始め、藤原道長は病から回復し、67代「三条天皇」とさらに対立するのです。
雲隠の意味
まぼろしの巻
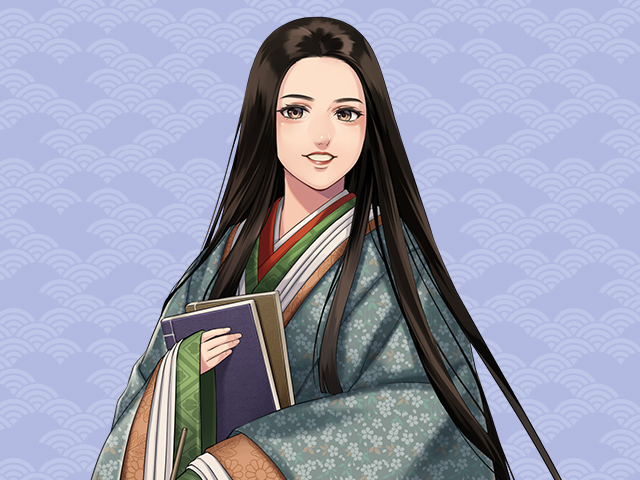
紫式部
病になる直前、まひろを訪れた藤原道長は、紙に書かれた「雲隠」(くもがくれ)という言葉を見ました。「雲隠」という言葉は、高貴な人の死を意味する言葉でもあり、42話の作中では源氏物語の光源氏の死を意味していると思われます。
しかし、この直後に藤原道長は激しい頭痛に襲われているので、藤原道長の生涯がひとつの終焉を迎え、新たな人生が幕を開けることを暗示しているのかもしれません。
ちなみに源氏物語において「雲隠」は、巻名だけが伝えられ、内容は伝存しない謎の巻です。第2部の最終巻であるとされているのですが、「本文はあったが失われた」という説と、「最初から巻名だけで、紫式部は本文を書いていない」とする説があります。さらに南北朝時代に書かれた源氏物語の注釈書である「原中最秘抄」(げんちゅうさいひしょう)には大変興味深い話があり、それによると「雲隠」には光源氏の死が描かれており、これを読んだ人々が世を儚んで次々と出家してしまったため、時の天皇の命令により内容を封印してしまったと言うのです。
このように内容が不明なことから神秘性はさらに深まり、今も昔も愛好者達にとって「雲隠」は、憧れと好奇心の対象となっています。
もうひとつの雲隠
「雲隠」と聞くと、百人一首に採られた紫式部の和歌を連想する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲隠れにし 夜半(よは)の月かな」
<現代語訳>何年かぶりに会った女友達のあなた。でもそれは、ほんの束の間で、夜半に沈む月と争うように早々と帰ってしまった。
ここでの「雲隠」の意味は文字通り、月が雲に隠れた、という意味だとされています。しかし、源氏物語の謎の巻と同じ単語が入った歌が、百人一首に採用されているのは単なる偶然でしょうか。
百人一首は、平安時代末期から鎌倉時代初期の歌人である「藤原定家」(ふじわらのていか)が選んだ秀歌撰です。藤原定家は、自ら写本を作るほどの源氏物語愛好者でした。その藤原定家が、数ある紫式部の和歌のなかからこの一首を採用したのは、「雲隠」の文字に神秘的な魅力を感じたせいではないか、と筆者には思われてなりません。
藤原道長と三条天皇の駆け引き

藤原実資
42話では、藤原道長と三条天皇の間で、ぎりぎりの綱引きのようなやり取りが見られました。三条天皇が藤原道長の娘である「藤原妍子」(ふじわらのきよこ)を中宮にすると宣言したのは藤原道長にとっても喜ばしいことでしたが、おそらくそれは次の一手を実現するための布石だったのでしょう。翌月、三条天皇は、長年の妃である「藤原娍子」(ふじわらのすけこ)を皇后にすると言い出します。
藤原道長は、藤原娍子が大納言の娘に過ぎないことを理由に反対しますが、三条天皇は「ならば二度と藤原妍子のもとには渡らぬ」と言い、取り引きの材料にしました。
仕方なく折れた藤原道長でしたが、ただ受け入れただけではありません。藤原娍子の立后の日に藤原妍子の内裏参入の日をぶつけたのです。三条天皇も、立后の儀の時間帯をずらして対抗しますが、結局、現れたのは、「藤原実資」(ふじわらのさねすけ)、「藤原隆家」(ふじわらのたかいえ)、「藤原懐平」(ふじわらのかねひら)、「藤原通任」(ふじわらのみちとう)の4名のみであり、寂しい立后となりました。
藤原実資の日記「小右記」によると藤原実資は、自邸で宴を催している藤原道長に使者を使わして藤原娍子立后の儀に参入するように促したようですが、公卿達は使者を前に出して笑ったり、罵ったりし、あげくには石を投げる者までいたと言います。
さらに藤原道長自身、娘・藤原妍子の内裏参入の宴へ来なかった人物の名と、各々に対するコメントを、自身の日記「御堂関白記」(みどうかんぱくき)に書き付けているのです。公卿達がどちらに出席するかによって、敵か味方かを見極めたかったのでしょうが、藤原道長は根に持つタイプに見えますね。
42話は、新たな人生への岐路となった回でしたが、次回43話「輝きののちに」では、病から回復した藤原道長がどのように三条天皇に立ち向かうのでしょうか。また、予告で藤原道長の正妻「源倫子」(みなもとのともこ/りんし)が呟いた「殿に愛されてはいない」という言葉の真意は何なのかなど、来週の「光る君へ」も目が離せません。




























