光る君へ 39話「とだえぬ絆」 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
あらすじ(2024年10月13日放送分)
1009年(寛弘6年)11月、中宮・藤原彰子は、第2子となる「敦良親王」(あつながしんのう)を出産しました。土御門邸では、「産養」(うぶやしない:小児誕生の夜を初夜とし、その日から、3、5、7、9日目にあたる各夜に行われる出産祝いの宴)が開催され、公卿達が参じています。しかし、その中に、右大臣の「藤原顕光」(ふじわらのあきみつ、演:宮川一朗太[みやかわいちろうた])と内大臣の「藤原公季」(ふじわらのきんすえ、演:米村拓彰[よねむらひろあき])の姿はありませんでした。
年の暮れ、まひろは、年末年始を過ごすため、父・藤原為時の屋敷へ戻ります。そして、藤原道長から藤原賢子へ贈られた「裳着の祝い」の絹織物を見せると、あまりの豪華さに家族達は驚きました。このとき、藤原惟規が「やっぱり自分の子はかわいいんだな」と発言。藤原惟規の言葉によって、藤原為時は、藤原賢子の父親が、まひろの亡き夫・藤原宣孝ではなく、藤原道長であることを知るのでした。
衰弱して床に伏していた藤原伊周のもとへ、弟の藤原隆家や息子の「藤原道雅」(ふじわらのみちまさ、演:福崎那由他[ふくざきなゆた])が見舞いに訪ねてきます。無念の思いを告げる藤原伊周に、藤原隆家は「(藤原定子の皇子である)敦康親王様のことはお任せください。安心して旅立たれませ」と伝えました。藤原伊周は、わが子の藤原道雅に「藤原道長には従うな。低い官位に甘んじるくらいなら出家せよ」と最期の言葉を残します。そして、翌日、36歳という若さでこの世を去りました。
同じ頃、体調を崩して弱気になっている一条天皇は、藤原行成に、敦康親王が次の東宮になるための道筋を作っておきたいと相談します。敦康親王の元服を急いでいる一条天皇に、藤原行成は、すでに日取りを陰陽寮に相談していることを伝えました。それを聞いた一条天皇は、藤原彰子の出産に紛れることなく、敦康親王の元服を世に示すことができると安心します。
一方、藤原彰子の妹「藤原妍子」(ふじわらのきよこ、演・倉沢杏菜[くらさわあんな])が藤壺を訪ねてきました。藤原妍子は、現東宮「居貞親王」(いやさだしんのう:のちの三条天皇[さんじょうてんのう]、演:木村達成[きむらたつなり])の后になることが決まっています。しかし、居貞親王には、すでに「藤原娍子」(ふじわらのすけこ、演:朝倉あき[あさくらあき])という后がおり、藤原妍子は不満を隠せません。藤原妍子は、藤原彰子に、自分達姉妹は、父の藤原道長が権勢を握るための道具なのだと伝えます。苦言を呈するまひろでしたが、藤原妍子は「うるさい」と言い残し、藤壺を出ていきました。
やがて「元服の儀」の前日になります。敦康親王は、藤原彰子にこれまでの感謝を伝え、別れを惜しみました。敦康親王は涙ぐみながら、なかなか藤原彰子の手を離そうとしません。その光景を見た藤原道長は、「敦康親王様が『光る君』の真似をされたら一大事だ」とまひろに伝えます。「光る君」とは、まひろの書いている「源氏物語」の主人公であり、義母に想いを寄せ、不義密通に至った人物。藤原道長は、敦康親王がそれを真似るのではないかと心配をしているのです。まったく取り合わないまひろでしたが、藤原道長は、敦康親王が元服したあとには、住まいを移すように仕向けるのでした。
1011年(寛弘8年)正月、藤原惟規が「従五位の下」(じゅごいのげ)に昇進し、藤原為時が越後守に任命されます。しかし、藤原為時の供として越後へ向かう途中、藤原惟規は突然、激しい腹痛に見舞われ、帰らぬ人となってしまいました。
藤原惟規の死は、すぐに内裏にいるまひろに知らされます。まひろは、急いで屋敷に戻ると、涙に暮れている藤原賢子といとに、藤原惟規の「辞世の歌」を読み聞かせました。しかし、気丈に振るまっていたまひろですが、ついに涙をこぼしてしまいます。藤原賢子は、そんなまひろの姿に「母上でも泣くのね」と、そっと寄り添うのでした。
ライターのつぶやき「たとえ死しても…途絶えぬ絆」
藤原伊周、呪詛の果てに
妹の声を聴いて迎えた最後

藤原伊周
藤原伊周は、死の淵にあってもなお「俺が何をした。父も母も妹もあっという間に死んだ。俺は奪われ尽くして死ぬのか」と藤原道長への恨みを口にしていました。
しかし、前回となる38話の狂乱した様子と比べると、病のためか弱々しくもあります。そして兄・藤原伊周の死に際を、涙しながら静かに見守る「藤原隆家」(ふじわらのたかいえ)の姿も印象的でした。
藤原伊周が朦朧とする意識のなか「今日は雪遊びにいたしません?兄上」という妹「藤原定子」(ふじわらのさだこ)の声を聴き、ひそやかな笑みを浮かべた藤原伊周は夢現ながら「雪だ」と呟きます。まるで、藤原定子が藤原伊周を迎えに来て、あの世へと導いたのではないかと思えるほど美しい演出。そして藤原伊周は、その翌日、息を引き取ります。
藤原伊周が「雪だ」と呟いた通り、藤原定子は実際に雪と縁の深い女性でした。「清少納言」(せいしょうなごん)の書いた「枕草子」(まくらのそうし)には、内裏に雪山を作り、いつまで雪が残るか賭けを行った話が描かれていますし、「香炉峰の雪」(こうろほうのゆき:清少納言が藤原定子の問いに応じて、御簾を巻き上げたエピソード)の話もあります。さらに、鳥辺野で藤原定子の葬儀が行われた日は大雪が降ったため、藤原伊周は雪のなか藤原定子を見送ったのです。そのときに藤原伊周が詠んだ歌がこちらになります。
「誰も皆 消え残るべき 身ならねど ゆき隠れぬる 君ぞ悲しき」
<現代語訳>
人は誰も皆、決して永遠には生きられないが、今はただ(雪の中に)逝ってしまったあなた(藤原定子)のことが悲しい
藤原伊周と藤原定子は、どちらも父「藤原道隆」(ふじわらのみちたか)が興した一門「中関白家」(なかのかんぱくけ)を守ろうと、強い絆で結ばれた兄妹。しかし不運なできごとが重なり、挙げ句、政治抗争においては藤原道長に屈する形となり、藤原伊周・藤原定子は不遇のまま最期を迎えました。けれども清少納言が描いた枕草子では、藤原伊周・藤原定子両名の優れた人物像と、藤原定子の華麗で雅やかだった登華殿(とうかでん:藤原定子の局)の様子を現代まで伝えています。
藤原惟規の死
最期まで姉想いだった弟

藤原惟規
39話ではまひろの弟である藤原惟規が従五位下に叙せられ、乳母「いと」が「上向いて参りましたよ、ご運が」と言い、藤原惟規と親子のように抱き合い喜ぶ場面が描かれました。そしてまひろと藤原惟規の父「藤原為時」(ふじわらのためとき)も越後守(えちごのかみ:現在の新潟県の国司)への任官が決定。さらにまひろの娘「藤原賢子」(ふじわらのかたこ)の裳着(もぎ:女性が行う成人の儀)も無事に執り行われるなど祝い事が続きます。
裳着の晩、藤原惟規は女性に振られたことを理由に、気分転換をしようと父・藤原為時を越後国まで送るとまひろに告げました。そこへ、藤原道長のまひろに向けられる深い想いを引き合いにだし、藤原道長の変わらない愛情は「とてもすごいことだ」と称えるのです。
こうして藤原惟規は、藤原為時と共に越後国(現在の新潟県)へ向かうのですが、その途上、藤原惟規は急に腹痛を訴えます。そして藤原為時の懸命な看病の甲斐もなく瞬く間に世を去ってしまうのでした。藤原為時からの手紙で藤原惟規の死を知らされたまひろ、藤原賢子、いと達が悲しみに暮れる姿は、非常に重苦しく涙を誘う場面に。藤原惟規による辞世の歌がこちらになります。
「都にも 恋しき人の 多かれば なほこのたびは いかむとぞ思ふ」
<現代語訳>
都にも恋しい人がたくさんいるゆえ、なんとしても生きて帰りたい
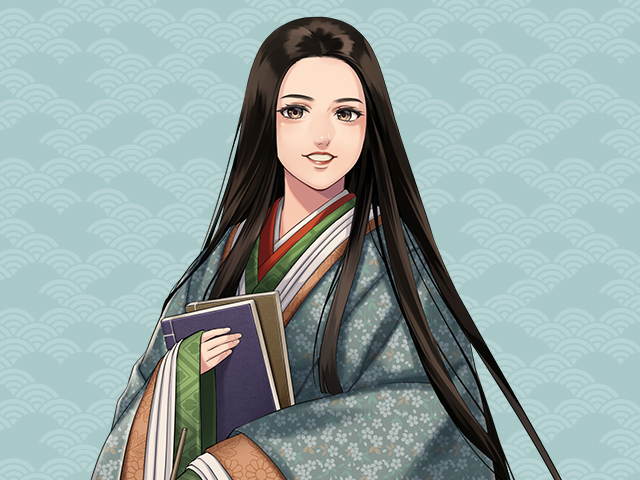
紫式部
手紙を持ち、弟が最期の瞬間まで懸命に書いた歌を口にするまひろは寂しげな面持ちでしたが、このときまだ涙はありませんでした。けれども読み終えたところから徐々に涙をこぼし、泣き崩れてしまいます。
そんな母の涙を見た藤原賢子は、悲しみを分かち合うようにまひろの肩を抱き寄せました。藤原惟規は亡くなる間際まで「左大臣様に賢子のことを…」と口にするほど、まひろと藤原賢子のことを心配していましたから、まひろと藤原賢子の距離が少し縮まったことを知ったら安心するかもしれません。
自然を愛でた藤原惟規
藤原惟規の人柄と臨終の様子を書いた書物には、平安時代末期の歌人「源俊頼」(みなもとのとしより)によって書かれた歌論書「俊頼髄脳」(としよりずいのう)があります。「俊頼髄脳」には、「藤原惟規は、先に越後へ到着した藤原為時を追って都を出発したものの、途中で病になり、父のもとに着いたときすでに危篤の状態だった」というように書かれているのです。藤原為時は息子・藤原惟規の死を覚悟し、死後の安楽を願って僧侶を招きます。
しかし僧侶は驚くべきことに「このままでは(藤原惟規は)地獄へ行くことになる。しかも来世が決まるまでの間も中有(ちゅうう)という、鳥や獣さえもいない寂しい場所をさまよい歩くことになるぞ。その心細さ、人の恋しさは例えようもない」と、藤原為時と藤原惟規に話をしたのです。
僧侶は続けて「地獄に落ちないよう、仏縁にすがり、身も心も御仏に預けるように」と告げるつもりだったようですが、藤原惟規は息も絶え絶えのなか「そこでは嵐にともなう紅葉や、風にしたがう尾花の下で、松虫や鈴虫の音などが聞こえないのか?」と尋ねます。僧侶は、なぜそのようなことを聞くのかと問うと、藤原惟規は「それらを見れば心が慰められるだろうから」と答えました。死を前にして出家する気のない藤原惟規にこれ以上、仏法を説いても仕方がないと判断した僧侶は退出したと「俊頼髄脳」にはあるのです。
当時における貴族らの死生観として、死を目前とする人々は、極楽浄土へ行くことを願い、出家するのが一般的でした。それに反して、風流を愛する藤原惟規は死ぬ前の出家よりも死後も歌を詠める環境であるかどうかを重要視していたのです。勅撰和歌集の「後拾遺和歌集」(ごしゅういわかしゅう)にも和歌が採択され、自身の和歌集「藤原惟規集」(ふじわらののぶのりしゅう)もあるなど、藤原惟規は優れた歌詠みの才を持っていました。「俊頼髄脳」には、自然を愛でる心を最期まで持ち続けた藤原惟規の人柄が滲んでいるように思えます。
派手好き、贅沢好きの藤原妍子
39話には、「藤原彰子」(ふじわらのあきこ)の妹であり、藤原道長と「源倫子」(みなもとのともこ)の次女「藤原妍子」(ふじわらのきよこ)が登場。藤原妍子は東宮である「居貞親王」(いやさだしんのう:のちの67代三条天皇[さんじょうてんのう])の后(きさき)となることが定められていました。

居貞親王(三条天皇)
当時、63代「冷泉天皇」(れいぜいてんのう)を祖とする冷泉系と、64代「円融天皇」(えんゆうてんのう)を祖とする円融系という皇統が隆盛し、この2つの血統が交互に皇位継承を行っている時代。
このことから藤原道長は、冷泉系か円融系どちらの皇統が続いても自分が外戚となり権力を持てるよう、円融系の66代「一条天皇」(いちじょうてんのう)に長女・藤原彰子を、冷泉系の居貞親王に次女・藤原妍子を入内させたのです。

藤原彰子
しかし藤原妍子は、居貞親王が18歳も年上であること、自分が父から政治の道具扱いされていることに不満を抱き、姉の藤原彰子に愚痴をこぼします。道具に例えたことをまひろが「そのようなお言葉はご自身を貶められるばかりかと」とたしなめると、藤原妍子は「なんかうるさい、この人」と気分を害した様子を見せました。
藤原妍子は、思慮深い姉・藤原彰子とは対照的に、やや物事を浅く考える人物として描かれているよう。けれども、藤原妍子にしてみれば、父親が絶大な権力を維持し続けるための苦痛を引き受けているわけですから、不満を持つのも当然な状況と言えるのかもしれません。
39話において藤原妍子は、連日宴を催しているとされ贅沢好きな性格が窺えました。実際の藤原妍子も、毎日のように宴を開き姉の藤原彰子がそれに難色を示したという話が、「藤原実資」(ふじわらのさねすけ)による日記「小右記」(しょうゆうき)の1013年(長和2年)2月25日条に記されているのです。華美なものや贅沢を好み自らの宿命に不満を持っている藤原妍子が、「光る君へ」の物語にどのような影響を与えるのか、今後が楽しみですね。
さて、39話ではこの世を去る人達と、残される人達の絆が描かれましたが、次回の40話「君を置きて」では、いよいよ次の東宮(とうぐう:皇太子)を誰にするかという「立太子問題」が表面化しそうです。波乱の展開を見せる来週の「光る君へ」も目が離せません。




























