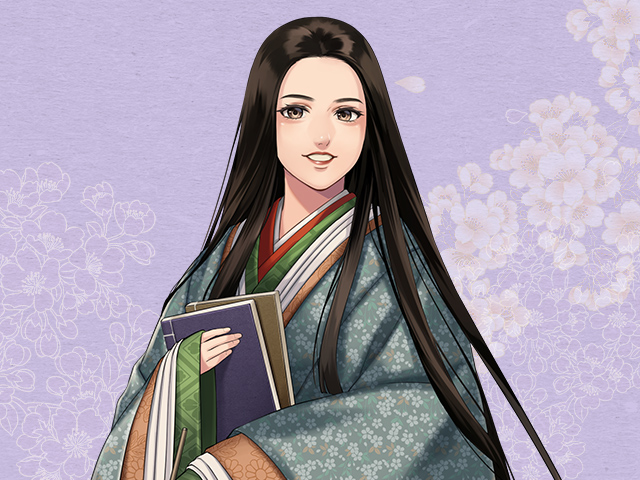紫式部の供養塔がある「慈眼堂」 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
慈眼堂の歴史

慈眼堂
慈眼堂は、「慈眼大師」(じげんだいし)とも呼ばれる天海僧正が祀られている廟所です。天海僧正は「織田信長」による比叡山焼き討ちの際、「比叡山延暦寺」(滋賀県大津市)の復興に尽力した人物。
「徳川家康」、「徳川秀忠」(とくがわひでただ)、「徳川家光」(とくがわいえみつ)の3代にわたって将軍家に仕えました。
さらに「日光東照宮」(栃木県日光市)や「東叡山寛永寺」(とうえいざんかんえいじ:東京都台東区)など高名な寺社を創建するという功績を残しています。
慈眼堂の成り立ち
慈眼堂は、天海僧正を祀るために建てられました。建てられた年代の具体的な史料はありませんが「天台座主記」(てんだいざすき)などによると、1646年(正保3年)と伝えられています。なお、慈眼堂には、歴代の天台座主(てんだいざす:比叡山延暦寺の最高位を持つ僧)の墓が存在。
特徴的な景観
慈眼堂の特徴は、宝形造(ほうぎょうづくり)や禅宗様といった建築様式。宝形造とは、平面が正方形だったり八角形だったりする建物にみられる屋根の形で、隅棟(すみむね)がすべて中央に集まる形をしています。
なお、禅宗様の建築様式が見られる建造物としても知られており、火灯窓(かとうまど:灯火をともす器具の形をした窓)や頭貫木鼻(かしらぬききばな)に彫刻が施されているところなどに特徴があるのです。
また、中央間には吹寄菱格子(ふきよせひしごうし)など、和様の建築要素が組み込まれているのも慈眼堂の特徴。正面には石灯篭(とうろう)が2列に並び、厳かな廟所の雰囲気が感じられます。慈眼堂の西側には阿弥陀仏や延暦寺の歴代座主の墓、五輪塔なども存在する、静かな廟所です。
慈眼堂に供養塔がある平安時代の人物
慈眼堂には歴代座主の墓の他、様々な人物の供養塔を見ることができます。平安時代の人物で、小倉百人一首に和歌が登場する、慈眼堂に供養塔が建てられている3名の人物をご紹介しましょう。
慈眼堂の詳細情報
| 施設の正式名称 | 延暦寺慈眼堂 |
|---|---|
| 所在地 | 〒520-0113 滋賀県大津市坂本4-6-1 |
| 電話番号 | 077-578-0130 |
| 営業時間 | 境内自由 |
| 休業日 | 無休 |
| 料金 | 境内自由 |
| 交通アクセス | 京阪坂本比叡山口駅から徒歩5分 |
| 施設詳細ページ |
※外部サイトへ遷移します。 |