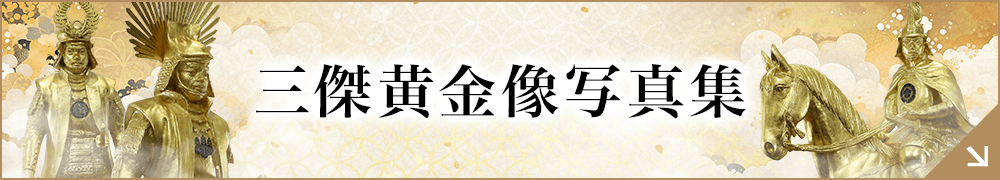三英傑の黄金像と金無垢太刀(純金24金) - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
華やかな風格が漂う三英傑の黄金像
立像の高さは人の腰ほど! 騎馬像はさらに大迫力
外から観ることができる三英傑の銅像が等身大に近い大きさで、躍動感たっぷりに刀を掲げているのに対して、黄金像は大きさこそ銅像には及ばないものの、大軍を率いて敵軍を睨み付けているような、まさしく天下人の風格と華やかさをまとっているのが特徴です。人の腰くらいの高さがあるその全身はまばゆいほどの金色に包まれ、鑑賞する人の目を釘付けにすることは間違いありません。
この「三英傑の黄金像」が鑑賞できるのは、本館3階の「武将ゾーン」です。黄金像の展示ケースの背面には、遠目にも分かりやすいよう三英傑それぞれの家紋が大きく掲げられています。また、60分の1のスケールで精密に再現された「名古屋城」(愛知県名古屋市中区)の模型のすぐ隣なので目に留まりやすいでしょう。

金色に輝く騎馬の織田信長

織田信長の黄金像
悠然と馬を進める姿に戦国の覇者としての威厳が漂う織田信長像。
兜の前面を飾る前立はヤク(体毛の長いウシの仲間)の毛を用いたとされる矢羽根(やばね)で、西洋風にも見える甲冑の胸元には「織田木瓜」(おだもっこう)の家紋があしらわれています。
馬の鞍(くら)にもあるこれらの家紋のみが黒色に染められており、家紋が金色の銅像とは反対の配色となっているのです。


黄金が似合う天下人・豊臣秀吉

豊臣秀吉の黄金像
織田信長の後継者となり、天下を治めた豊臣秀吉の黄金像は右手に軍配を持ち、左手を太刀(たち)の鞘(さや)に添えた立ち姿で表されています。
戦場を見据え、今まさに軍配を振るわんとする気概が見えるようです。
兜は、まるで黄金が光を放っているような「一の谷馬藺後立付兜」(いちのたにばりんうしろだてつきかぶと)。また、天下人となった豊臣秀吉は黄金の茶室を作るなどしたことから、金色がイメージカラーとされることが多く、誰よりも黄金が似合う天下人と言えるのではないでしょうか。


徳川の黄金期を築いた徳川家康
製作は三英傑の銅像と同じ「(有) 田畑功彫刻研究所」

織田信長公像
三英傑の黄金像は、富山県高岡市を拠点とする胸像・銅像の製作所「有限会社 田畑功彫刻研究所」が手がけました。
本館入口にある銅像を製作した会社であり、これまでに製作した胸像・銅像・仏像・モニュメントなどの作品は1,000体以上という実績を誇っています。
田畑功彫刻研究所の作品としてよく知られているのは、JR「岐阜駅」の北口広場前に立つ黄金の「織田信長公像」です。像の高さは約3m、台座を含めると高さは約11mになります。3層の金箔を重ねて張った立像は、織田信長の武功を示すように輝き、駅前のシンボルとして行き交う人々を見守っているのです。「名古屋刀剣ワールド/名古屋刀剣博物館」(名博メーハク)で展示されている三英傑の黄金像では、この岐阜駅前に立つ織田信長像に通じる匠の技を観ることができます。
間近で鑑賞できる金無垢の太刀拵
武将ゾーンの中でも、ひときわまばゆい輝きを放っているのは三英傑の黄金像だけではありません。たいへん珍しい金無垢の太刀・太刀拵(たちこしらえ)も三英傑像とともに鑑賞することができるのです。
展示されている4振は、いずれも金具類に金無垢(きんむく)を用いて繊細な装飾を施した美術品。金無垢とは、一般的には混じりけのない純金のことを指しますが、金の含有量が75%の18K(Karat:金の純度を示すカラット)を含む場合もあります。純金はやわらかく傷付きやすい素材であるため、銀や銅など他の金属を混ぜて装飾に使用したのです。これらの金無垢太刀・太刀拵について、1振ずつご紹介していきます。

金無垢太刀拵(きんむくたちこしらえ)
純金純銀亀甲紋様飾り太刀拵
(じゅんきんじゅんぎんきっこうもんようかざりたちごしらえ)
「純金純銀亀甲紋様飾り太刀拵」は、1979年(昭和54年)に「内閣総理大臣賞」を獲得するなど、数々の受賞実績を持つ金工作家「光則」(みつのり)氏により制作されました。純金(24金)1,220gと、純銀600gを使用した本太刀拵の鞘には、古くから長寿の象徴として尊ばれてきた亀甲文様が施されています。極めて繊細な表現を追求した光則氏の真髄とも言える妙技が堪能できる作品です。

純金純銀亀甲紋様飾り太刀拵
金置平目鞘金無垢菊紋金具糸巻太刀拵
(きんおきひらめさやきんむくきくもんかなぐいとまきたちごしらえ)
「金置平目鞘金無垢菊紋金具糸巻太刀拵」は、重要美術品の「太刀 銘 一 鎺下ニ菊花紋ノ切付アリ」に付属する太刀拵で、鍔や目貫などの金具類には金無垢が用いられています。「菊紋」があしらわれた鞘に使われている技巧は置平目。置平目とは、金・銀・錫(すず)などを鑢(やすり)で削った鑢粉を1粒ずつ置いていく方法で、華やかな仕上がりになるのが特徴です。

金置平目鞘金無垢菊紋金具糸巻太刀拵
金梨子地菊紋散蒔絵鞘金無垢総金具糸巻太刀拵
(きんなしじきくもんちらしまきえさやきんむくそうかなぐいとまきたちごしらえ)
「金梨子地菊紋散蒔絵鞘金無垢総金具糸巻太刀拵」は、「太刀 銘 備州長船利光 嘉慶四年二月日」に付属する太刀拵で、総重量1,376gの金無垢が使われています。蒔絵(まきえ)の一種である金梨子地(きんなしじ)の鞘には菊紋があしらわれ、格調の高さがうかがえるでき映えです。梨子地は金銀粉を蒔いた上に透明の漆を塗って文様が見えるようにした技法。
鎌倉時代にはじまったと伝えられ、梨の表面に似ていることから名付けられました。

金梨子地菊紋散蒔絵鞘金無垢総金具糸巻太刀拵