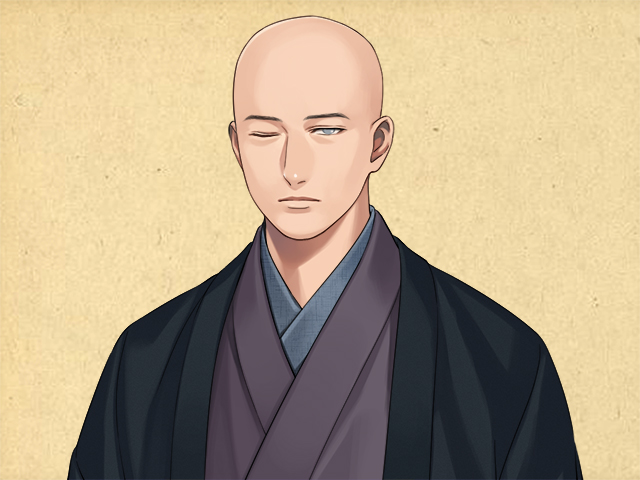べらぼう13話-② 「米価次第だった武士の給料」 - ホームメイト
- 小
- 中
- 大
大名から庶民まで借金が日常的だった江戸時代
用途に応じて細分化していった金融業
借金返済のために吉原へ身売りする女性も多かった
江戸時代は借金に関する法律が整備されていなかった時代です。そのため、座頭金では年利が平均して6割、なかには10割などの法外な事例もあったと言われています。また、借金の時効もないため、親の借金を子供が支払うケースも珍しくありませんでした。借金を一度に返済するために吉原へ身売りする女性も多く、特にもとは裕福であった商人や、武士の娘が身売りする場合、そのほとんどが、親の借金返済が理由となっていたのです。
武士の給料が米価に左右された理由
技術の進歩が米価の下落を招く

「富嶽三十六景 江戸日本橋」前北斎為一(葛飾北斎)筆
江戸時代、領地を持たない武士の給料は、主君から米で支払われていました。年貢として農民から徴収した米を、武士にそのまま給料として宛がっていたのです。武士は、このいわゆる「俸禄米」(ほうろくまい)を売って現金を得ていましたが、その作業を代行したのが札差でした。
米は需要が高ければ価格が上がり、低くなれば下がります。そのため、江戸幕府は米価の調整に苦労しました。8代将軍「徳川吉宗」(とくがわよしむね)が「米将軍」(こめしょうぐん)と呼ばれていたのは、なんとか米価をコントロールしようと尽力したからです。
「蔦屋重三郎」(つたやじゅうざぶろう)が生きていた江戸時代中期は、技術の進歩によって、江戸時代初期に比べると米を増産できるようになっていました。しかし、豊作になるほど米の希少価値が下がるため、米価も下落してしまいます。そして武士の給料も米価に比例して下がり、武士の生活は苦しくなっていったのです。
米価を決めた堂島米会所

「浪花名所図会 堂じま米あきない」歌川広重 筆
江戸時代において米は経済の基盤でしたが、価格を決めていたのは武士ではなく商人でした。大坂の堂島(どうじま:現在の大阪市北区堂島浜)に設置された「堂島米会所」(どうじまこめかいしょ)に全国の年貢米が集められて商人達による売買が行われ、その価格で全国の米価が決められたのです。
堂島米会所で決まった米価は、米を介しての金・銀・銅の交換比率にも影響を与えたため、米価が決まり次第、全国に伝えられました。その際に用いられたのが旗振り通信です。「米相場早移」(こめそうばはやうつし)と称した旗振り通信は、旗や提灯を用いて行われ、最盛期には現在の大阪から和歌山まで、3分で相場の価格が伝わったと言われています。その情報伝達速度はなんと時速720km。電話を利用するスピード並みに、情報が江戸まで運ばれていきました。
次回の放送は2025年4月6日(日)、第14話「蔦重瀬川夫婦道中」です。蔦屋重三郎と「瀬川」(せがわ)の初恋は実るのでしょうか?来週の「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」も目が離せません。
【国立国会図書館デジタルコレクションより】
- 「富嶽三十六景 江戸日本橋」 前北斎為一(葛飾北斎)筆
- 「浪花名所図会 堂じま米あきない」歌川広重 筆